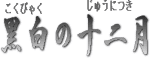 弥生・黒 / 白 「 帰る雁 弐 」 |
|||
| <壱へ | 参へ> | ||
非番の日は寝坊しがちな同心だが、今朝は明け六つに目覚めていた。 朝餉を終えてひとりで出かけるつもりだったのに、子どもが離れようとしない。日頃忙しいこともあって非番の日の同心は極端に甘く、それを見透かされてしまっている。 「しょうがない。一緒に散歩するか」 「さん、ぽ。さんぽ」 「いいんですか?」 「おまえもだ。俺ひとりじゃ扱いきれない」 「はいはい」 朝の仕事も終わってないのにと口では文句を言いつつ、女房もいそいそと支度にかかった。着流しに羽織りをまとう。身支度をすませれば最後は刀だ。 今朝に限っていつもの備前長船でなく、筑後左文字を手にしていた。同心として晴れて奉行所につとめることになった折に剣の師から譲り受けたもので、父の形見の次に大事にしている。 なぜと自分でも不思議に思ったが、こういうときは心の動きに逆らわぬ方が良いと経験から知っている。ままよと脇差しと二本差しにした同心は、二人とともにそろって家を出た。 侍は同心の手回しにより奉行所にずっと留められていた。八丁堀からさして遠くない。頃合いを計りながらゆるゆると数寄屋橋をさして進む。 子どもは抱かれてもじたばたとおとなしくはせず、下ろせば目についた興味へと脱兎のごとく走り出すという具合で、女房と代わる代わる追いかける羽目になった。それでも、ようやく柔らかさを帯びた春風の中を親子水入らずでの散策はのどかなものだ。 非番の日に家族を連れて奉行所前まで行くつもりはない。橋のあたりで侍が来たら声をかけ、送ろうと同心はそう考えていた。 数寄屋橋のたもとでなくかなり手前にしたのは、女房が橋近くに長く子を止めたがらないとわかっていたからだ。 「すまぬが、このあたりで少し人を待つ。先に戻るか?」 「大丈夫よ、たぶん」 女房はちょろちょろとかけずり回る子に油断なく眼をやりながらそう言った。「たぶん」は「きっと」よりもさらに不確かだ。 三人の居る川沿いの狭い通りを、黒土を積んだ荷車がごろごろ大きな音で走り抜ける。その車から土が少しずつ流れ落ちていた。道の上に、ついて来いと言わんばかりに跡が残されていたら大人だって気を誘われよう。三つになるかならぬかの子どもは言うまでもない。 目を丸くして荷車を見送っていた子は、ぱっと弾かれた矢のように後を追って駆けだした。 「おい!」 同心の方が近かった。女房もあわてる。 「あなた?」 「待ってろ。連れて戻る」 叫ぶや走り出した夫と、その向こうの子どもを女房は気を揉みながらも見送った。岡っ引きと侍が、橋を渡りながらやってきたのはまさに、そのときだった。 遮るもののない空を見上げるのは久しぶりだった。奉行所から出たそこに岡っ引きの姿を見て、侍は驚きそれから笑んだ。本当に人のいい男だ。彼にも、彼の上役にも大きな借りができたと思う。 「良かったな」 多くを言わず肩を叩く岡っ引き。昔よりもずっと思慮深く懐の深い男になったものだと、侍は時の流れをしみじみ感じる。ふたりは歩をそろえて橋へと向かった。 「持ち物は返してもらえたか」 「刀だけだからな。手入れが必要だが時が惜しい」 「だろうな」 岡っ引きに侍の心情は読まれているらしい。鳥になれるものならすぐにでも飛んでいく、そんな思いを。 「旅にはいい頃になった」 「そうだな」 ぽつぽつと話すうちに橋にかかる。越えたら岡っ引きと別れ、まっすぐ東海道へと侍は進むつもりだ。ふと隣が妙な声をあげた。 「お内儀じゃないですか」 すっとんでいく先、橋から少し離れたところに武家風の女がこちらを向いて立っている。妙にぽかんとした顔に浮かんでいる喜びと驚き。岡っ引きがさらに問うている。 「お一人ですか。旦那は?」 「三人で来たんだけど、子どもを追いかけて今、あっちへ」 「坊ちゃんを?」 岡っ引きが旦那と呼ぶのは同心のことだろうかと考える。なら、女はその妻ということになる。それにしてはまじまじと向けられた視線が奇妙だった。 面識はないはずだが。どこかで会った? 気のせいか。岡っ引きの手をつかんだ女の声は上擦って聞こえる。 「ねえ、この人は」 「いや、その」 岡っ引きが口ごもるのも無理はあるまい。放免になったといえ今朝まで奉行所にとらわれていた男を、仮にも同心の妻にひきあわせるのはどうか。 行った方がいいと思った時、侍は首筋にぴりぴりとした気配を覚えた。 まずい。 「おい」 岡っ引きを呼ぶ。相手も感じ取ったらしいのはさすがだ。 「ここで別れよう。世話になった。同心にくれぐれも礼を言ってくれ。あんたの女房にも」 「しかし」 「お内儀のそばを離れるなよ」 岡っ引きに釘を刺す。ここで同心の身内にとばっちりを食らわせるわけにはいかぬ。それは岡っ引きとて重々承知のはずだ。侍の言葉になぜか女まであわてて見えた。 「待って、あの」 「ごめん」 侍は駆けだした。街道目指して。幾人もの気配を引き連れて。 女房は呆然としていた。追わなくては。でも足が動かない。 岡っ引きと一緒に現れた男はまさしく、半年前に川に飛び込んで我が子を助けてくれたあの浪人だった。 なぜここに。 岡っ引きと一緒ということは、同心が待っていたのはこの人なのか。 渦巻く疑問をよそに浪人は突然その場を走り去っていく。いけない。ひと言の礼も言えてないのに。おろおろするだけの自分がもどかしい。そんな自分をみて岡っ引きもまでおろおろしているのが可笑しい。めちゃくちゃだ。 「どうした」 うしろから声をかけられてぱっとふりむいた。走り疲れたのかおとなしく抱かれている子どもと、夫。伝えなくては、早く。気ばかり焦った。 「あの人よ」 尋常でない顔で飛びかからんばかりにして胸元にくらいついてくる女房に、同心はぎょっとたじろいだ。 「あの人なの、助けてくれた人」 「……いたのか? どこに」 言わんとしていることを察して思わず同心は周囲を見回す。するといつ来たのか、岡っ引きが困惑気味に言葉を挟んでくる。 「旦那。侍を送りに来てくださったんで?」 「あ? ああそうなんだが。そういえば侍は」 「行っちまいましたよ。へんな奴らに追われて」 「何?」 「だから、あの人なんだってば!」 割り込むようにして女房が叫んだ。ちゃきちゃきの町娘だった頃そのままだなと、思った矢先でようやく意味を悟る。 「……侍が? まさか」 「誰かなんて知らないけど。橋を渡って来た浪人がこの子を助けてくれた人よ。間違いないわ!」 穏やかな日差しの下だというのに同心はめまいを感じた。 奉行所の仕事に携わっていると人と人とのつながりや因縁に驚きを覚えることが多い。右と左の全く異なる事柄が、思いがけぬ鎖で結ばれる不思議を幾度も眼にした。自分にまでそんなことが起きようとは。 子を救ってくれたのが侍だというなら、それはとりもなおさず水門屋と斑に追われて江戸に出てきた頃だ。自分が侍を捕らえ、助けることになったのは、三年前の岡っ引きとその女房との縁から。 どれが始まりで何がきっかけだったのか。誰が誰を救ったことになるのか。いや、今はそれどころじゃない。同心は岡っ引きに聞き返す。 「追われてたって? 侍はこのまま江戸を出るのか?」 「そのはずで。追っ手はひとりじゃなかった。俺にはさっぱり」 「まずい」 子どもを女房に手渡した同心は、強い口調で言い含める。 「先に戻ってろ。奴がこの子の恩人ならなおさら、急がにゃならん」 「あなた」 「あとで話す。いいから戻れ、まっすぐだ」 「はい」 女房も同心の妻として、うるさく聞いていい時と悪い時は心得ている。岡っ引きが焦れる。 「旦那?」 「斑だ。おまえも来い」 「ま、まだらぁ? げ、なんで……まってくれ、旦那!」 通りを突っ走っていく同心とこけそうになりながら追いかける岡っ引きを、女房は今度も見送った。浪人が、この子の恩人がどうか、無事でありますように。 はしゃぎ疲れた子どもはぐずりはじめている。あやしながらも、小さな両手が真っ黒なのを見てなぜか涙がにじむ。どうか神様。 女房は祈ることしかできなかった。 侍にとって江戸はどこよりもなじんだ土地だった。少なくとも縄張りとしていた辺りでは、どの道がどこへつながってどう閉じているか知り尽くしていたし、逃げると決めて逃げ切れなかったことなどなかった。だが三年の不在の上多勢に無勢、おまけに相手は斑ときている。 不利だな。 走って逃げている最中というのに、自分が笑っていることに気づき、さらに可笑しくなる。悪くすれば命の瀬戸際、余計なことを考えている場合ではなかろうに。思うそばから反論が湧いて返る。だからどうしたと。 頭はこの上なくすっきりしていた。ふた月囚われの身だったから身体はなまっているが、だからこそこうして力一杯走るのは快感だ。怖いものなどない。何より固い意志があった。江戸を発つ。侍の中でそれは決まった事柄であり、邪魔するものに容赦する気はない。 来るなら来い。また口元がゆるむ。危ないなと自分で思った。ずっと感情を抑えてきた反動かもしれぬ。容赦する気はないが、放免されたばかりで下手に騒ぎをおこせば、自分の首を絞めることになるのもわかっていた。 ふっと背後の気をよける。だんと板壁につきささったのは、くない。忍者しのびもの の投げ道具だ。斑はこんなものも使うのか。身に迫った危険は切実だ。 細道をかくかくと曲がり商店にとびこんで裏へ抜ける。さらに曲がったところで誰かにぶつかってしまった。老人だ。 「う、わ」 「っと、すまぬ」 「おとっつぁん?」 よろめく身体を支えたところへ女がとんできて老人をかばった。威勢のいい罵声も飛ぶ。 「ちょっとあんた、どこみて……え。 お、まえさ、ん?」 面と向かい合ったのはあの女だった。半年前、見事にはめてくれた女。その眼に去来する様々な感情は複雑すぎるし、構うひまなどない。 きびすを返した背中にもう一度、声。 「ねえ」 肩越しに振り返る。詫びなど聞く気はなかったが、枝のように細く痩せた老人を抱えながら、女は言った。 「まだ油売ってたのかい。あの娘っこのとこへとっととお帰りよ。帰って、江戸には二度と来ないことさ。そうだろ?」 きつい言葉もしかめた眉も似つかわしいが、潤むまいとする眼だけがらしくなかった。その言葉が、詫びなのか。言えるのはただ。 「達者でな」 侍は駆けだした。 それきり二度と、女に会うことはなかった。 参へ >> <壱へ |
|||
| <Home <侍目次 <十二月扉 | <如月・黒へ | 弥生・白 | 卯月へ> |