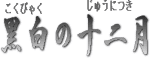 弥生・黒 / 白 「 帰る雁 壱 」 |
|||
| 弐へ> | |||
「お帰りなさい。早かったのね」 「たまにはな」 月番にしては確かに早い帰りだった。タコ同心を女房が使用人と出迎えたのは長屋でなく、同心の生まれた家だ。 町人の娘だった女房を娶めと るまでにはいろいろなことがあった。しばらくはふたりだけでやっていこうと長屋暮らしを選んだのは父や世間に対する同心の意地。もっともその長屋は父同心の所有、実家とは目と鼻の先だったわけだが。 その後の父の急逝は思いがけなかった。こんなことならわずかな間でも三人で暮らすのだったと、同心の密かな悔いは女房しか知らぬことだ。思い出が辛くて、時折手入れには行っても戻ろうとはしなかった実家へ、我が子の誕生でようやく移ってもうじき三年になる。 女房の後ろから廊下をだだっと走る音がした。喜び勇んで飛びついてきた息子を同心は高々と抱き上げる。 「ち、ち、うえー」 「坊主、昨日より重くなった。大きくなったな」 「うん」 あり得ないことを大まじめに言う、同心の立派な親馬鹿ぶりに女房も笑いを堪えている。 ようやく授かった一粒種の息子はふたりにとってまさに掌中の珠、眼の中に入れても痛くない。再びここで家族と過ごせることが同心は嬉しかったし、きっと父も喜んでいると信じている。 三人そろっての夕餉にすっかりはしゃいだ子どもは、食べ終わるか終わらぬうちにぱったりと力尽き、同心の膝で眠り込んでしまった。まるでねじの切れたからくり人形だなと苦笑するが、愛しさはつきない。 「どんどん大きくなるな」 「無茶なことばかりするの」 「男はそんなものさ」 杯を手に笑うと女房が聞く。 「なんだかとっても嬉しそう」 おおらかな女は夫の心に敏さと い。仕事については差し障りも多いので日頃はあまり語ることをしない同心だが、今日は珍しく漏らす。 「例の侍、お裁きが決まった。明日放免になるそうだ」 「まあ良かった」 女房の言葉は追従ついしょう ではなかった。年明けに捕らえた侍について深い事情は知らぬが、夫である同心と古なじみの岡っ引きが頭を悩ませ苦労していたのを知っているからだ。 「ほっとしたのね」 「まあな。死罪なんてことになったらあいつに何を言われるか。このふた月、うるさくてしょうがなかった」 「だって、無実なんでしょう?」 「この件に関しては、な」 女房の注ぐ酒を受けながら、同心を去来する思いは複雑でもあった。 番頭のことを思い切った水門屋は、店での不正や横領、押し込み強盗についても残っている限りの証拠を差し出し、身内の使用人にも証言させた。 おかげで侍についての疑いはさっぱりと消すことができ、同心の下調べは吟味与力にも賞賛された。お調べがすべて終わったあと同心は逆に問うたほどだ。 「ここまでやって斑まだら から文句は来ないのか」 水門屋にけっと軽くいなされる。 「あっちは俺の思惑なんぞ頓着しねえよ。だから番頭もあっさりやられちまったろ」 言われてみればそのとおりだ。 「つまり、侍が安心するのもまだ早えってことだぜ」 「どういう意味だ」 いぶかしむ同心に水門屋は周囲をはばかり声を潜める。 「おそらく。斑はまだ侍につきまとう」 「なんだと」 「江戸を離れる時が一番危ないな」 「おいそりゃ」 「侍をやたらと構いたがる天狗がいてな。昔ちょっと関わったせいか。番頭をやった夜、侍が煮え切らなかったからもっぺん性根を見たいんだとさ」 「いったいなんのことだ」 「俺の知ったこっちゃねえよ。要はだ、そのうち侍はでかい襲撃に遭うだろうってことさ。道中も続くかな。京まで持ちこたえりゃそれでお構いなしだ、たぶん」 同心は頭の中でぐるぐると情報を並べ替える。 「……伝えていいのか」 侍に、という意味だ。肩をすくめる水門屋。 「前もって聞いときゃ対処もできるだろ」 「対処ってな。放免直後に騒ぎをおこしてみろ、あっというまにお縄で今度こそお仕置きだぞ」 「俺もそこまでは面倒みきれねえ」 水門屋は最後は笑っていた。確かに襲撃を予告するのが精一杯の義理というところだろう。 その後、奉行所で水門屋の言葉を伝えたが侍はまるで動じなかった。 「いろいろ世話になった。感謝する」 深く下げた頭は誰に対してだったのか。 捕らえられて黙りこくっていたひと月を越えて、諦めの影は消え静かな明るさだけが侍を包んで見えた。あれならやってくる窮地も切り抜けるのではないか。切り抜けられなかったら? それも仕方ないと考える自分は冷徹なのかもしれぬ。明日、出てくる侍を迎えに行くと言った岡っ引きにも教えてやるべきだったろうか。正直、同心は水門屋の台詞に同調する気持ちもある。 『そこまでは面倒みきれねえ』 侍は決して正義の者ではない。今回の件も元をたどればすべて、侍の身から出た錆というやつだ。良きにつけ悪しきにつけ、自分のしたことは自分に返ってくる。いつまでも逃げることはできぬ。対峙すべきだと同心は思う。思いつつ気になるのも本心だった。 「どうしたの」 女房の声で我に返った。飲み干した杯を手に考えにふけっていたようだ。 「ほかにも難しいことが?」 「いや」 笑って打ち消した同心は心に決めた。明日は非番だ。岡っ引きに倣って侍を迎え、見送ろう。それがけじめというものだ。 ひとりで頷く同心に小首をかしげた女房が酒器を置いた。 「重いでしょう? そろそろ寝かせてきます」 「まだいいさ」 「だめよ」 「なら、俺も行こう」 杯を置いた同心は子どもを抱え立ち上がった。あわてて女房は先に立ち、寝間へ二人で向かった。 寝間着に着替えさせ布団に寝かせる。子どもの細々した世話を同心は日頃から厭うことがなく、慣れた手つきだった。触れられる手が誰か知っているのだろう、布団にくるまった子は笑みを浮かべ眠っている。 「寝る子は育つ、だな」 「ほんとに」 飽きず寝顔を眺めていた同心は、鼻をすする音に振り向く。 「おい、またか」 「ごめんなさい。いつになっても思い出されて」 潤んだ目を伏せる女房の肩をやれやれと言う顔で抱き寄せた。もう半年も前の出来事だというのに、女房は思い出すたびにこうして涙ぐむ。それもしょうがないかもしれぬ。もしかしたらこの子は冷たい死体になっていたかもしれないのだ。 半年前、女房に連れられて出かけた息子は、通りがかった橋から下をのぞき込んでいるところを運悪く、人波につきとばされて川へと落ちた。 梅雨の晴れ間。川はごうごうと勢いよく、泳ぎも知らぬ小さな身体はいまにものみ込まれそうだった。後から飛び込もうとして周りに抑えられ女房が絶望しかけた時、その流れに飛び込んで助けてくれたのは浪人だったという。 助け上げられた岸で水を吐き、泣き出した息子を抱きしめて震えが止まらなかったと、その夜女房から聞いた同心は恐怖と安堵でその場にへたり込みそうだった。ふたりで抱き合い涙をごまかし、無事を喜んだ。 悔いは、助かった子に夢中だった女房が命の恩人である浪人の名前も素性も聞かずじまいだったことだ。 「細身だったけどとても見事に泳いでいたわ。鋭い眼で総髪で、旅姿だったような」 覚えているのはそれくらい。子どもの一大事に無理はなかった。 今も町に出るたびに女房は浪人を探しているようだが、すでに半年経つ。江戸にはいないかもしれぬ。会えたとして命を救ってくれたことに何を返せるわけでもないが、同心もせめてひと言、礼が言いたかった。健やかな寝顔を見ればなおのこと。 「見知らぬ子どものために梅雨の流れに身を投じる。なかなかできることじゃない」 「ほんとうに。毎晩拝んでいるの、あの人にどうぞお礼ができますようにって」 「そうだな。俺も祈るか」 女房の髪の香をかぎながらつぶやいた同心は、日頃深く神や仏を信心しているわけではなかったが、翌日。 天の配剤を知ることになる。 高窓の格子の向こう、白々と夜が明けていくのを奉行所の仮牢で侍はじっとみつめていた。 雁が見える。 帰っていく雁が。 ここから出られる、それ自体とても運がいい。尽力してくれた同心と岡っ引きがいなければ出るどころか、有無を言わせず死罪を被ったかもしれぬ。わかっていたから時間がかかるお調べも耐えられた。辛くはなかった。昨日、お沙汰が下って本当に放免されるのだと知るまでは。 今も飛び出しそうになる自分を必死で抑えている。早く。京へ。時の流れにこんなにも焦れたことはない。 同心から伝えられた水門屋の警告はさもありなんと受け止めた。あの夜、斑が侍を放置したのは水門屋が恨みに思うのを知っていたからだろう。侍に逃げ場はないと。 ところが水門屋は気持ちを変え、侍は自由になる。このまますんなり江戸をたてるとは思えなかった。できれば平穏にと願ってはいたが仕方あるまい。 ためらいも迷いも捨てたいま、心は逸る。 時が惜しい。 何が行く手を阻もうと明日は必ず立つ。 京へ。 昇る陽に焦がされて燃え上がる空の色も、影のように渡る雁も、侍の心そのままだった。 弐へ >> |
|||
| <Home <侍目次 <十二月扉 | <如月・黒へ | 弥生・白 | 卯月へ> |