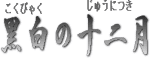 如月・黒 / 白 「 萌芽 参 」 |
|||
| <弐へ | |||
「おう、入ってくれ」 すっと開いたふすまの向こう、水門屋みなとや は形ばかりかしこまっていたが、顔には警戒心と反抗心が隠すことなくあらわにされていた。 タコ同心にとっては見慣れた表情だ。三年前、水門屋をお縄にしたのは他ならぬ同心なのだから素直にやってくるわけもない。案の定、ぶっきらぼうな声を投げてくる。 「何の用だ」 「なんだと思う」 ニヤニヤ笑うと、海千山千の水門屋がげんなりしてそっぽを向いた。同心が水門屋自身に負けず劣らず食わせ者なのはよく知っている。だからといって同心からの呼び出しを無視もできまい。 仕方なく部屋に入った水門屋は差し向かいに胡座をかいた。奉行所や同心など恐れてないと見せたいのだろう。そこで問う。 「斑まだら ってのは」 ぎょろっと、水門屋の目の玉だけが同心へ吸い付いてくる。 「正体不明のようで、実はいろいろ上に繋がってるのか」 「上ってなんだよ」 岡っ引きがいる以上、斑についてはとぼけてもしようがないと悟っているようだ。 「一介の同心にそこまでさぐらせるほど甘くはねえようだが。素性はおぼろげに浮かんでるぜ」 「素性?」 「願人がんにん、とか」 身構えた水門屋の警戒は今度こそ本物にみえた。 この時代は公家をかざした武士が頂点の身分社会だ。武士も町人も貧富の差は激しいが、身分にはさらに下がある。えた、非人と呼ばれる被差別民衆は彼らだけの集団を形して「弾左衛門」が彼らを支配し、「弾左衛門」を通じて彼を頭と定めた幕府の支配をも受けていた。 一方、弾左衛門の支配を受けぬ被差別民もいる。願人がんにん はそのひとつだ。大道芸を生業とする点では、弾左衛門支配下の乞胸ごうむね とよく似ているが、願人は成り立ちを京都鞍馬寺の僧侶に端を発するという。故に取り締まりも寺社奉行の管轄で町奉行所には手出しが難しい。 そこがタコ同心の注意を引いた。神出鬼没で情報に長けるという斑まだら。 裏を返せばさりげなくそこここにいて、様々なことを見聞きしていると考えられる。大道芸を行う願人のように。加えて端を発するのが京都とくれば。 同心はさらに聞く。 「おまえさん。上方の出だってな」 「ああ?」 「鞍馬の方とか。天狗に知り合い、いるんじゃねえの?」 ぐっと喉で蛙かわず を押しつぶすに似た声で呻いた水門屋は、それを呑み込むと居住まいを正しタコ同心をはったとにらんだ。敵愾心てきがいしん に満ちた目つきだ。 「旦那」 「ん?」 「触らぬ神にたたりなしってのはほんとのことだぜ」 「神様か」 がちとかみあわさる視線。どちらも退かぬかと思いきやふっと同心が眼を和ませる。 「そうとんがるな。俺が聞きたいのは神様天狗様のことじゃなくおめえさんのことだ」 胡散臭げに片眉をあげた水門屋へ同心はさらに続ける。 「昨日。 侍はちゃんとしゃべったぜ、全部」 皺の寄った目元、実はつぶらな水門屋の眼まなこ が見開いた。 「侍の話と岡っ引きの話は、抜けてるところはあっても食い違いとか矛盾はねえ」 同心の口調が真面目に変わる。 「だが、一味がほぼ死んじまったから、番頭がそのひとりだったと証明出来る者がいねえ。番頭の死が自業自得か、それとも罪がなかったのかで侍の立場はぐるりと変わっちまう。死罪か、追放か」 強いまなざしが水門屋を捉える。 「だから聞きたいんだ」 「何を」 「おめえさんだってこうしてお仕置きから生きて戻ってきてるってのに。侍に死罪を望むほど恨んでるのか?」 ぴんと張っていた水門屋の背中が不意に崩れた。大きく肩を上下すると正座が再び胡座に戻る。うなだれこそしないもののうつむいた目線。やがて同心に向けた顔はうすい笑みで強張っている。 「どうだかな」 ぎしと、うすい唇の奥で噛みしめた歯の音に水門屋の心中が垣間見えるようだ。 「旦那。俺はあんたのいうとおり上方の生まれだが江戸の水の方がもう長え。気持ちは江戸っ子よ。ちゃきちゃきのあんたに言いたかねえが、過ぎたことを恨みつらみするのは江戸っ子じゃねえだろ。俺の性分でもねえ」 確かにそうだろうと同心も思っている。直接でなくとも、長く見てきた水門屋とはそういう男だ。だからこそ不思議なのだ。 「あんたの問いは半分当たってる。俺は侍に恨みをはらしてえ。でも理由は俺がお仕置きされたからじゃねえよ。俺が捕まらなきゃ番頭はこんなことにならなかったからだ」 「捕まらなきゃ?」 「そうさ。俺がそばにいればあいつはあんな馬鹿なことをしなかった。たとえ考えてもできなかったはずだ」 言い切る水門屋の顔は暗い影を帯びる。同心は幾度も会ったことのある番頭の、死に顔を思い出した。 同心にしてみれば番頭は如才ない小利口な男で、水門屋の金をかすめたことといい押し込み強盗といい、まさかそんなことをするようには見えなかった。刑期を終えて戻った水門屋はどう思ったのだろう。 「旦那、子どもはいるか」 「やっと三つだ」 「かわいいだろ」 「そりゃな」 「あいつはな、番頭は八つで親に捨てられた」 突然飛んだ話に同心は目を丸くする。 「物乞いやらこそ泥やら掏摸すり のまねごとやらで、なんとか生き延びてたらしい。十とお の時、俺の懐を狙いやがったのを捕まえてぶん殴った。それから丁稚でっち としてひきとったんだ」 「どうして」 問われてぼんやり視線だけがこちらへ向く。 「さあな。血迷ったんだなきっと」 自らを嘲るような笑みは、暗い。 「可愛げはないしこすっからいし。捨てられてからの二年が骨身にしみちまって他人を信用できないしさ」 「そりゃしょうがねえかもなあ」 「なのに寂しがりでひとりが嫌いで。いつもあがいてやがった」 水門屋の声音の甘さが同心を戸惑わせる。自分の店と命を狙われたというのに。 「知ってのとおり俺には実子がいねえ。女房の連れ子、あれは女のくせに気が強くて反抗的でな。番頭のことは白状するなら息子みてえな気がしてた」 恥をうちあけるみたいに目を伏せる水門屋の小さな声。 「小心者で小ずるくて、番頭にまでなったくせに客も商売もつかみきれねえ。だから手元に置いたんだ。俺のそばで得意なことだけやらせておこうと思った」 「……あんたはあいつを、息子として信用してたんだな」 静かな部屋。水門屋は片手で、禿は げあがった頭を幾度もなでた。掻きむしる髪がないのを悔しがるかのように。 「小金をくすねるくらい実の親相手だってやるだろ? その程度ですむはずだった。それくらいかまやしなかったんだ。俺が、長く店を空ける羽目にならなきゃ」 ゆっくりと這い上がってくる視線。 暗い海をたたえた眼。 水門屋が番頭をそれほどまでに思っていたと、気づかなかったのは娘である岡っ引きの女房もだろう。我が子が死んだら。たとえそれが本人の落ち度でも親は、誰かに責めを負わせずにはいられないのだろうか。 三つになるかならぬかの息子を同心は思い浮かべた。親になってまだ短いがあの子のためなら何だってする。もし死んだら? 考えたくもない。万が一殺されるなんてことがあれば、きっと。 犯人を必ず。 そうかと同心は腑に落ちた。 だから水門屋は番頭の非を認めようとしないのだ。 斑まだら が番頭に約定の責を、死をもってあがなわせることは承知していたはずだ。水門屋にはそれは止めようがなかった。代わりにせめてと思ったのか。愚かな子を思う身勝手な親の、これもまた深い情なのかもしれぬ。 同心もさすがに説得の言葉を探しあぐねた。何気なく懐に手を入れる。そこで託された物を思い出した。 「そうだ、これ」 手のひらにのせて差し出す。はじめぼんやりと見た水門屋がゆっくり焦点を合わせるのがわかった。見開かれる小さな眼。そっと伸ばされた指が震えている。 「どうして」 「番頭のらしい。大事にしてたんだな。自分で求めたのか誰かにもらったのか」 「おれ、が」 水門屋から言葉がこぼれる。 「ひきとった次の年にえびす講へ連れてってやったんだ。金を稼ぎたいってそればかりいうから、商売の神様にお参りするかって。御利益があるよう買ってやった守り袋だ。礼も言わず、でも握りしめてたっけ」 記憶をたどりながら水門屋が、額をこする。 「二十年も昔の話だ。まだ持ってたなんてな。金はくすねるわ約定は破るわ、あげく押し込みまで企みやがって。俺を、独り立ちさせてもらえなかったことを、さぞ恨んでたんだろうと思ったのに」 鼻の頭にぎゅっとしわが寄る。堪えている感情を同心が推し量る。 「斬られる間際、懐で握りしめたそうだ。侍が拾って持ってたらしい。おめえさんにって」 「侍が? 俺に?」 ごつごつした手の上の守り袋と同心を、水門屋は信じられぬという顔で見比べる。 「ほかに身内を知らねえから。供養してやれってさ」 うつむいた水門屋は守り袋を握りしめた。身体が震える。 「ばかだなあいつも俺も。……いや番頭が一番か」 悼むような憐れむような、愛しむようなつぶやきを同心は黙って聞いた。 それぞれの考えに沈んでしばし、顔をあげた水門屋は憑つ きものが落ちたみたいに明るい、でも皮肉な笑みを浮かべていた。 「しょうがねえ。侍についちゃ元々、俺の逆恨みなんだからからあきらめてやるか。でもな旦那、斑は俺みたいには、俺ほどには物わかりよくねえぜ、たぶん」 どういう意味だと聞く前にまず、同心はその気になった水門屋から番頭についての事実をきちんと聞き取らねばならなかった。まだ何かを孕んでいる口ぶりが気になったが。 なんとか侍を死罪はもちろん入牢させることもなく解放してやれそうだ。岡っ引き夫婦に良い知らせができると、今はそのことに安堵している同心だった。 牢内で、侍は待っている。 はやる心をこらえ、娘からの文を幾度も読み返しつつ。 三日後、侍は町奉行所へ移された。吟味役のお調べを受け、江戸十里四方払いのお裁きで解き放たれたのはさらに二十日後。 雪の下だった萌芽はもう蕾に変わり、春の到来を告げていた。  < kisaragi-kuro / End > <弐へ |
|||
| photo / EyesPic | |||
| <Home <侍目次 <十二月扉 | <睦月・黒へ | 如月・白 | 弥生・黒へ> |