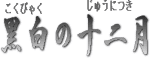 睦月・白 閑話 / 黒 「 雪笹 」 |
|||
朝、いつもと変わらず道場に出てきた浪人に、前夜から娘のお産が始まっていると告げたのは他でもない老師だった。ざわりと胸が騒ぐ。 「もうしばらくかかるだろうよ」 期待と心配の入り交じった、師には珍しい興奮の色を見取って浪人は苦笑する。たとえるなら孫を待つ心持ちなのだろうか。 「生まれるんやて」 「そらめでたい」 来る者来る者、挨拶代わりにその話ばかり。命の誕生はそれほどに心踊るものだ。誰もが母子の無事を願い心配しているのに安堵する。気になるのは自分だけではないと。 おかげで稽古も浮き足立ったが、今日ばかりは浪人もきつくとがめ立てできなかった。自分も似たりよったり、まだまだ修行が足りぬ。昼を過ぎると人も少なかったので早めに切り上げることにした。 生まれたとの知らせはまだない。気にしてたむろしていた者達も三々五々いなくなった。浪人はひとり雑巾を手に道場を拭き清める。いつものことだがいつもより念入りだったのは、依然落ち着かない気持ちを静めるためでもあった。 (まるで自分の連れ合いのお産だな) 水桶でぎゅっと雑巾をしぼりながら思った。そこで手は止まる。肩が固まる。ぽたりと滴が桶の真ん中に落ちて円をつくるのを見下ろす。 己だけのものである心が何故、己の知らぬ芽をはぐくむのだろうか。 ふっと力を抜いた浪人は絞った雑巾と水桶を手に外へ向かった。 老師の家近くにある長屋に、浪人は二年前から棲み暮らしている。六畳一間の一人所帯。布団と身の回りの物しかない暮らしは始めこそ荒れていたが、この頃は掃除洗濯もまめでこざっぱりとしている。近所の女房達には「亭主に爪の垢でも煎じて飲ませたい」と賛辞されるようになった。 それもこれも老師の道場で代稽古の仕事を得たからこそだ。 年も身分も様々な者が通う道場で教えることはなかなかに難しく、始めは何かと自己嫌悪に陥ったりもした。それでも続けられたのは自分の力というよりも、教えを受ける側が辛抱してくれたからだと思う。若造の足りぬ指導を汲み取ってくれるおおらかさが彼らにはある。 それにしても先の師範代は教えることが上手かった。自分が教えることになってからより強く思う。 浪人がここに出入りするようになったのは昨年正月。ふとした機会に老師の穏やかで枯れた美しい剣技を眼にした。門を叩いた道場で体調が良くない老師に代わり代稽古をしていた男に、老師とは別の計り知れなさを感じた。 もっともその大方は奥に隠され、代稽古はいわば切っ先だけで足りていた。決して手を抜いているとか遊び半分なわけではない。誠意を持って教えている証拠に門人達からも慕われていたが、実力は小指の先しか出していない。いつだか老師にそう漏らしたらほのかに笑んで言った。 『あれはな、ここに居る者達のためだ。白い剣だけ教えておるのだよ』 意味を問い返したかったけれど、それきり言わぬつもりなのは見て取れたし、何よりも師の笑みに混じる深い情が浪人の口を封じてしまった。白があるなら黒もあるのだろう。如何なるものなのか知りたいと、思いはしたが口にすることはなかった。 男は誰に対しても同じ態度でばらばらな門人たちの実力・性格に添った丁寧な指導を続けた。浪人自身それなりの力はあると自惚れでなく思っていたが、彼にかかると子どものようにあしらわれてばかり。落胆する浪人に男は言った。 『強さと弱さは裏表、弱さから眼をそむけてはならぬ。強さは弱い自分の中に在る』 男の言葉は老師のそれに似て、浪人は咀嚼するたびに新しく気づかされることが多かった。 さほど親しくもならず、他の者と同じにただ毎日竹刀を交えるだけの間柄だったのに、なぜ男は稽古の代わりを自分に託すことにしたのか、今も不思議で仕方がない。昨春、桜が咲き始めた或る日だっだ。 『故あって京を離れる。ついては道場での指導を頼まれて欲しい』 唐突な頼みに驚き、即座に断った。自分に務まるとは思えなかったからだ。なのに相手は諦めることを知らず、毎日のように説得は続いた。押し切られたのは納得したからではなく男の気迫に根負けしたのだ。男が文字通り消えてしまったのはまもなくのこと。 今、何処でどうしているのだろう。 男に連れ合いがいるのは聞いていたし、道場の母屋でそれらしき姿も見たことはあったがいつも遠目で、面と向かって出逢ったことがなかった。神無月、物欲しげに柿を見上げていた若い娘とはまるで重なるところがなく、正直驚かされた。 ところが、最初に感じた幼さは会うたびに形を変えていく。明るく気さくで、妊っているのに身体を動かすことを厭わず、誰にも気を遣い心を砕いた応対をする。子どもどころかしっかり大人の、女だった。 母屋に移ってくると門人達やその家族ともうちとけ、にこにこと。そのくせ、一人になると空の彼方を見上げてばかりいた。出かけたきり帰ってこない男を待っている。まっすぐに、時に迷いながらもまっすぐに、待ち続けている。 それだけ心を傾けられている男を、羨ましいと思っている自分に今、気づいたのだ。 これはまさしく横恋慕というやつではないか。 桶の水を空けてまた汲む。井戸は深く真冬でも凍ることはない。身を切るような冷たさが必要だった。雑巾を入れるとすぐ濁り、黒くなる水に眼を凝らす。手を放せば沈んだ雑巾は見えなくなる。 清く正しい人間だなどと自分を思ったことはない。生きるに不器用で生きやすい道を辿った結果、あまり悪いことをせずにすんだ。好き合った相手もいたが、同じく不器用で縁はすぐ切れてしまった。 ややこしいことは苦手だ。難しいと思うと最初から避ける、それですんできたのに。こんな風に不意に落ちてくる気持ちはどうしようもない。帰らぬ男に焦がれながら子を産もうと苦しんでいるひとに、横恋慕など。 黒い水に手を突っ込み雑巾をつかむ。水を幾度も代えて濁らぬまで洗い上げた。縁側の床下に桶と共に片付ける。ふと、母屋の方に嫌な気配を感じた。道場に置いてあった刀を手にとって返す。 広い庭は雪で覆われているが、お産のためだろう、いくつもの足跡が門と勝手口を結んでいる。それもまたいでぐるり、裏手へ回った。 笹藪のひと葉ひと葉がずっしりと雪を乗せていた。夕日が射しているはずなのに暗い。嫌な気配が強くなってくる。 この気は何だろう。 人か? 人ならあまりにも。 ばさっと、音がしたのか何かが触れたのか、確かなことは分からぬまま、本能で浪人はとびのいた。眼を瞬く。白昼夢かと思う。 赤ら顔。高く長く伸びた鼻。落ちくぼんだ眼。 大きな背に大きく広がる黒い羽が雪も空も遮る。 天狗? 馬鹿な。いくら否定しても眼をこすってもそこにある姿は溶けもせず消えもしない。 『おぬしか』 自分を知っているかのように声が響くが、口は動いて見えない。頭の中で木霊こだま する。 「何者」 『おぬし、あの娘。欲しくはないか』 ぎょっとした。いましがた自覚したばかりの気持ちを、この世のものと思えぬ相手に言い当てられるとは。やはり夢か。 『腹の子が流れれば、黒い男は帰らぬだろう。さすれば手に入るやもしれぬな』 夢に違いない。 ありもしない、あってはならぬ醜い思いをそそのかす、邪悪な夢。 『そう願わぬか』 なのにおちくぼんだ眼がなぜ、玻璃のようにきらきら輝いて見えるのか。囚われそうだ。 咄嗟にまぶたをとじた。すぅと息を吸い、はぁと吐く。 声は止まぬ。 『願うだろう?』 鯉口を切る。刀を抜いた瞬間気合いを発した。奇妙な顔の真っ正面に切っ先を振り下ろす。 「破っ!」 気配は消えた。暗かったはずが他と同じ、日を照り返す明るい笹藪。夢から覚めた心地だ。本当にいたのだろうか。白昼夢を見ただけか。 自問する眼前、ひらひらと舞い落ちたのは黒い羽だった。さしのべた浪人の手のひらをすりぬけて落ちる。雪の上に黒い墨のような。 ……んぎゃあ んぎゃあ 自分の後ろ、母屋から紛れもない赤子の声がした。命が漲みなぎ る。 「生まれた」 「生まれたなあ」 「良かった」 賑やかなのは心配して集まっていた隣近所だろう。貧しくとも温かな心が集まるのは、老師夫婦と娘の人柄故だ。 もう一度うつむくと黒い羽はやはりそこにあった。夢ではないらしい。あれは何者なのか。 『願うだろう?』 願わぬ。 自らを戒めるように呟く。 悲しむ娘も命が消えるのも、待つ人の不帰も決して願わぬ。 けれど。 母屋から陽に輝く藪へと視線は泳ぐ。 折れそうなほど雪をのせながらしなって耐える、雪笹のような女ひと を。 望まぬとは言えぬ。 横恋慕でも。叶わぬと知っていても。 気づいてしまった思慕を迷わず断ち切れぬ己の弱さ、未熟さ。 浪人は苛立ち、深く嘆息した。 母屋からは生まれたばかりの赤子が、今日を祝えとばかりに泣き続けている。 <mutuki-shiro kanwa-yukizasa / End> |
|||
| <Home<侍目次<十二月扉 | <師走・白へ | 睦月・黒 | 如月・白へ> |
|
↑押すだけで管理人へ届きます。 |
|||
|
kabegami/十五夜 |
|||