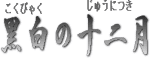 結び 「 そして、皐月 」 |
|||
| <質へ | |||
「きれいに衣替えだな」 「ほんと」 侍が抱いた赤子はあーうーと意味のない言葉をしきりに発しながら、一生懸命届かぬ葉を見上げて手足をばたつかせている。娘が見上げた桜は花をとうにぬぎすて、若葉で枝を覆いつくしていた。 侍と娘は赤子を連れて小さな家に戻っている。 朝は三人で家を出る。娘は宿へ、侍は道場へ赤子と一緒に向かう。日中はこれまでどおり、内儀に赤子を預けることにしたのだ。 道場での侍の処遇は宙ぶらりんだった。この一年、師範代を務めてきた浪人は侍が戻ったならと辞退しようとしたが、そんな身勝手はできぬと侍もこれを承知しない。 押し問答のふたりに、しばらく待てと口を挟んだのは老師だった。腕の立つ者を請う知り合いがいるという。すぐとはいかぬが、いずれどちらかに頼みたいと言われれば異論はない。それどころか願ったりだ。 そういうわけで当分は二人一緒に老師の道場に出向くこととなった。竜虎を迎えたと門人たちはやたらはりきってやってくるそうな。噂を聞いて新しい門人が増えたとも聞く。 赤子は日ごとに成長し、すっかり侍を虜にしていた。こんなにも赤子がおもしろいとは思わなかったと言う侍に、どこかで同じことを聞いたと娘は笑う。実際赤子については、侍と亭主は同じくらい親馬鹿になる。 「はじめの三月は俺が父親代わりだったんや」 「覚えてないだろ、はじめの三月なんぞ」 「ふん。赤子の覚えはふかーいところにあるそうやで」 「たかが三月。すぐ忘れるさ」 「なんやて、阿呆親父」 「なんだと、馬鹿亭主」 口げんかを遊びにしているとしか思えない。しまいに娘が赤子をとりあげてようやく終わりになる。使用人たちにまで笑われる始末だ。 誰もが侍の帰宅を喜んでくれた。娘が頑張ったからだと口をそろえて言われたが、娘にすれば皆の温かさがあったからこそだ。 侍が戻って数日後、昼休みに行った道場で師範代の浪人と顔を合わせた。穏やかに笑む人。 「無事に戻られて良かったですね」 「ありがとうございます」 この人に幾度助けてもらったか。 「もう、どこかへ行かせないように」 「次はついて行くんです」 娘がそう言い切ると、浪人ははたと口をつぐみ、それから大きな声で笑った。桜も終わり伸びゆく青葉によく似合う、明るい笑い声だった。 「あなたらしい。ほら、赤子が乳を待ってます」 会釈して母屋へ急ぎながら、肩越しに振り返ると浪人はまだ、笑っていた。温かな人に恵まれているとしみじみ思った。 侍との暮らしは一年前に戻ったような日々。 だが、同じようで同じではないと娘は感じている。 十二月を経て変わったのは自分か、侍か。両方かもしれない。たとえば見交わす眼と眼、触れる指先、笑み。ふとした折りに身を貫く愛しさは、かつてはなかったと思う。 なかったというなら、何よりも赤子か。新しい存在は否応なく二人の生活を変えていく。やがて言葉を覚えれば、父母ちちはは と呼ばれるのだろう。それもまた、楽しみだ。 花と葉を巡らせるこの桜も、毎年少しずつ大きくなっていく。変わらぬものはないのかもしれぬ。だが、育ちゆくものはある。 一年前はいなかった我が子を何より大事に思っている。赤子を抱いて笑うひとを一年前よりもずっと強く思っている。 この想いは次の十二月できっと、また美しく大きく育つ。 桜のように。 そっと微笑んだ娘の肩を侍が抱いた。侍に抱かれた赤子が目に見えぬ何かに手を伸ばそうとする。 降りそそぐ日差しが、地にくっきりと影を描いていた。 決して切り離せない白と黒。 互いをのみ込むことなく共に在る、それが選んだ形。 ふたりで綴れば、日々は鮮やかな錦絵だ。 鈴なりの若葉をふり仰いで赤子が喜ぶ。 顔を見合わせ笑いあう侍と娘。 ゆるりと三人を結んだ緑風は、白も黒も引き連れて、夏へと一気に駆け抜けていった。 < kokubyaku-no-juunituki / End > |
|||
| <質へ | |||
| <Home<侍目次<十二月扉 | <弥生・白へ | <弥生・黒へ | |
お気に召しましたら、ポチッとおしてやってくださいませv |
|||
|
photo / EyesPic |
|||