 霜月・黒 / 白 「霜柱」 |
|||
昔の、夢を見た。 江戸と京を気まぐれに行き来しつつ金になる話なら何でも乗った。弱い者いじめはしなかったと言いたいが都合によりけりが実際のところだ。 今日を暮らすだけの根無し草。昨日までの思い出も明日のための期待も身の内に持たぬ故、危ないことも平気だった頃。 斑まだら 天狗との関わりはただの行きずりだった。 彼らの噂は西から東まで知れ渡っていた。何者ともわからぬくせにすでに裏の世界で山頂のひとつ。正体不明の彼らに伝手を求め約定を結ぼうとする者が数知れないのには理由があった。 彼らは人の隠す内々の秘密、闇に葬られた内聞に通じているという。そればかりか噂で人を操ることもできるとか。神のような、でなければ天狗のような神通力があるとまことしやかに囁かれていたのだ。 また、結んだ契約・約定を破ることを許さず、万が一そんなことをすればどこまでも追いつめられて命を落とすとも言われていた。 「へえ」 酒を飲みながら侍は呆れた声を出した。 季節は秋。 熱燗が心地よく喉をとおる。 「約定を破るのを許さねえ? そりゃあ間違っても神さんじゃねえよな」 「なぜだい」 古びた旅籠にたまたま同宿した数人が安酒をさしあっている。 「神さん仏さんなら知ってるだろうからさ。人ってのは約束は破るし間違いを犯す、しようもねえ生き物だってことくらい」 笑いがそこここから漏れる。 「違ちげ えねえな。ついでに酒は飲む博打ばくち は打つ」 「酒は天狗も好きだろう」 「女もか」 「天狗に女は居るのか?」 何を言おうとただの噂だ。誰も会ったことがないのだから言い伝えの天狗と大差ない。すぐに色話に流れ、酒に飲まれて夜は更けた。 翌朝、ひとり涼しげな顔で侍は江戸へ向かって歩いていた。旅には丁度いい陽気も終わろうとしている。雪が降る前に江戸へ入るつもりだ。 夕べは大して飲んだわけでなく雑魚寝もいつものことだが、ひどくいびきをかく奴が居て閉口した。おかげで朝早く目が覚めたのでさっさと出立してきたわけだ。 山の中腹で笹原に出た。一本道だ。緑が枯れ色へと概ね変わっている。遠く連なる山が赤黄の衣をまとい群青の空に錦を掛け渡していた。冬へと散る華やかさには潔さもある。 毎年繰り返すようで同じ錦は二度とない。誰にもわからなくとも木が、枝が、葉が、織りなす柄はその年その秋その刻のみ。愛でられようと愛でられまいと限りを尽くして己を成す。心を持たぬ草木がそれをあたりまえとするのに、心を持つ人に難しいのは情けない。 自らをあざわらった時だった。笹原の向こう、一本道の真反対に男が現れた。しきりに振り返りながら今にも蹴躓きそうな足取りだ。目前でようやく侍に気づいたらしい。立ち止まり後ずさる。 脚絆きゃはん に手甲てっこうの旅姿。かっちり見えてどこか乱れている。まくりあげた小袖は片裾が落ち、町人髷は曲がって何より眼が胡乱うろん だ。 見るところはしっかり見る侍だが関わるつもりは毛頭無い。細い道を平然と行き違う。そこで二の腕をつかまれた。懐に手を突っ込まれてさらに驚く。 「助けてくれ、頼む、これをやるから」 「ちょ、おい、あんた何を」 「たの……わあっ」 すがりついたかと思うとのけぞって尻もちまでつく始末。唖然とした侍だが、相手の視線が自分の後ろに釘付けなのに気づく。同時に圧されるほどの殺気を感じた。 振り向いた侍が見たのは黒と白の群れだ。黒地に白が散った斑の装束を身にまとい、眼だけをのぞかせた一団が、笹原を半円一列に取り囲んでいる。ついさっきまで自分と男しかいなかったのに。 同じ装束とはいえ、背丈格好はずいぶんとちぐはぐで子どもかと思われるほど小柄な者もいた。全員が無言で侍の向こうにいる男をみつめている。ゾクリと侍の背筋がおののく。 ずいと列の後ろからひとり現れた。侍はその顔にぽかんと口を開ける。 なんだこれは。 とびでた額。それよりもっと突き出た長い鼻。深く落ちくぼんだ場所にはぎょろりと眼まなこ。切り込みを入れたように大きな口。天狗だ。赤い皮膚がつるつるしている。天狗の面だ。縁日か祭りか? 天狗面は侍の真向かいに立った。 「ひっ、あ、うわ、た、すけて」 座り込んでいた男はとうとう四つん這いだ。逃げようと必死に地面をかいているが、力が抜けているのだろう。ろくに前に進まない。 合図もないのに取り囲んでいた半円が数歩進んだ。列を乱すこともなく綺麗に前へ前へ。侍と天狗面を行き過ぎ、投網をすぼめるように逃げようとする男を捉えていく。侍は視線だけ追いかける。 「わっわああっ」 網が一気にすぼまったと思ったとたんに彼らは走り出した。中心に捕まっているはずの男ごと。 「はな、せっ、た、すけてくれ、えー」 輪の中に一瞬手が見えたものの。笹原を駆け抜け一団は見えなくなった。何が起きたのか。どうなった? わからないことだらけの侍は、怖れも忘れ答えを求めて天狗面へと向き直った。さっきから一言も発せず侍を睨んでいた面に問う。 「あいつをどうするんだ」 「煤竹すすたけ に鉛なまり というところか」 「何?」 「あの男は我らとの約定を破った上、金を盗んで逃げた。あがなわねばならぬ」 断罪が聞こえたかのように、彼方より絶叫がとどいた。長く尾をひいてふっつり途絶える。 こいつらが、斑まだら 天狗なのか? 見聞きしていることがあまりにも夕べの話を思いださせた。自らの眼と耳ををしても侍は半信半疑だ。驚きすぎて怖いとも思わない。天狗面が聞く。 「おぬし、連れか」 「違う。ここだけの通りすがりだ」 「それがまことなら、懐のものを返すがいい」 何のことかと胸元に入れた手が固い小さな包みに触れた。そういえばさっきなにか突っ込まれたな。取り出して驚いた。包み金だ。おそらく五十両。見たこともないとは言わぬが町人や浪人がそうそう拝める金高ではない。 すっと伸びた腕は毛むくじゃらだった。怯む間に金をつかむ手。急せ いた様子も浅ましい様子も見せず、天狗面はさらりと己の懐ふところ にそれを仕舞った。惜しいと思わぬわけではないが、面倒で文句はやめた。天狗面はそんな侍をじっと見る。 「黒いな」 肌色をそう言われたことはあまりない。どこか汚れているのかと着衣を見下ろし顔に手をやる侍。 「さっきの奴は元々冴えない色合いだったが、約定を破ってからは煤竹に鉛色、鉄さびまでごちゃごちゃ混ざって見苦しかったわ。それに比べれば見事なほど黒い」 「何のことだ」 「おぬしだよ。黒すぎる。わずかな白が星のようだ」 「あんた一体」 「ほっといてもろくな死に方をせんだろうから今日は見逃してやろう。あまり人を巻き込むなよ。おぬしの黒は他人を塗りつぶすほどに濃い」 尊大で高圧的な物言いは反論をさせない。 「我らに関わるな。どんな形であろうと、二度目は許さん」 鋭い眼光で射抜いてきた天狗面が、不意に地を蹴った。さして離れてもいない侍へ突進してくる。交わすことはおろか受け止める構えもとれず、侍は咄嗟に眼を閉じた。 来るべき衝撃はいつになっても来ない。開けた視界には揺れる笹原。誰も居なかった。ひとりきり。風にそよぐ笹が肌に鋭く刺すように感じられた。 「もし。まだお休みですか」 かけられた声に侍はとびおきた。自分の居る場所を悟るまで暫し。ここは、江戸での最初の夜に泊まった宿屋だった。 傷が快復してようやく動けるようになるやいなや、勝手に医者の処からここへ宿替えした侍だ。頼み事をしたので岡っ引きと女房にはいずれ連絡をとらねばなるまい。 「朝も召し上がっておられませんが、昼餉はどうされます」 「起きよう。頼む」 「承知しました。ところでちょっとよろしいですか」 ついと障子が開く。細い隙間から主人がするりと入り込む。ここの主人の身のこなしは影のようだ。目立たぬ所作が逆に侍の気を引く。 「今朝は冷えました。霜が立ったそうですよ」 「ふぅん。そうか」 平べったい夜具に胡座あぐら をかいてまだ覚めきらぬ顔の侍に、主人が声を潜める。 「以前も伺いました、くだんのお侍をご存じないでしょうか」 「何故」 問いに問いで返す侍に主人は黙る。待っている。ふーっと息を吐き侍は言葉を足した。 「知らぬでもない」 自分のこととは言わぬが、主人はおそらくわかっていよう。 「お渡し頂きたいものが」 「何」 侍のそばににじり寄った主人は膝に結び文を落とした。 「京からです」 「どうしてあんたに」 声をかける間に主人は障子の外へ身をすべらせている。 「蛇の道は蛇ですよ。昼餉はすぐに」 静かに閉まった障子は隙間もない。仕方なく侍は結び文を手にとり解いた。中身はごく短く。 『年明けに子が生まれる』 末尾の印は見覚えがあった。確かに亭主からだろう。子が生まれる。亭主の? まさか。知らせる意味がない。では……娘か。娘が子を産むのか。誰の? 行き当たって愕然とした。 自分の? ゆらりと、眩暈がした。真っ昼間なのにあたりが暗く思える。 いつも脳裏に思い浮かべていた娘が突然、身重の辛そうな姿に変わる。お産か。子を産むのは命がけだ。ひとりで産ませるのか。帰れるかどうかもわからぬのに。 それもこれも全て自分の。 自分が。 『おぬしの黒は他を塗りつぶす』 大の字に布団へ倒れ込んだ。忍び込んでくる冷気はひんやりと、さっきまであった温もりを消していく。 八方ふさがり。迷路に立つのはこんな気持ちか。 心に立った霜柱はくしゃりと潰れ、冷たく食い込むばかりだった。 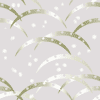 <simotsuki-kuro / End> |
|||
| <Home <侍目次 <十二月扉 | <神無月・黒へ | 霜月・白 | 師走・黒へ> |
| illust :Kigen | |||