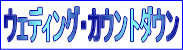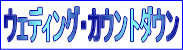|
雨音で眠った美羽は雨音で目覚めた。
昨夜遅くに降り出した雨はまだ止まない。明日の式も雨だろうか、それもいいかもしれないと思った。昨日も今日もそして明日も、変わらないものに安らぎを覚える。雨や太陽や、人が思いあう気持ちに。
式の前日でも両親は特に変わらなかった。いつもどおりの朝御飯は温の好みで和食だ。ご飯と味噌汁と目玉焼き。漬け物和え物。丈は朝はコーヒーが欠かせないから二人の朝はパン食になりそうだ。でも母のぬか漬けは気に入っていたっけ。そのうちに糠床を分けてもらおうか。うまく育てられたらいいんだけど。
「じゃあ行ってくるよ」
「行ってらっしゃい」
出勤する温を美羽は母と見送った。
同じ頃、丈も実家にいた。もともと前日は家で過ごすつもりだったので、昨夜、白兎家からまっすぐ戻ったのだ。両親の顔を見たくなったせいもある。
亀沢家の朝も和食、魚好きの謙介のために朝は干物と味噌汁が定番だ。子供の頃は飽きて嫌がったこともあったが、変わらないことは悪いばかりではないと今は思う。
「お代わり」
「朝からよく食べるわねえ」
三杯目をよそって差しだしながら道江がからかう。
「気をつけなさい。中年太りなんて美羽さんに愛想つかされるわよ」
「おいおい母さん、式の前日になんてこと言うんだ」
謙介があわてても丈は意に介さず納豆をかき混ぜる。挽き割りよりは小粒が好きだ。
「昨日まで飯どころじゃなかったんだ。出張でやせたくらいだよ。エネルギーを足さないと」
「あら、帰ったのは一昨日で昨日はゆっくりしてたんじゃないの」
かき込んだ納豆がのどにつまりかける。
「き、のうは寝だめに忙しかったから」
「道理で来るのも遅かったものね。一日寝てたわけ? 新婚初夜に花嫁ほっといて寝ちゃうよりましだけど」
ご飯までのどに詰まりそうだ。
「母さん、それセクハラだって」
「心配してるのよ」
「そりゃそうだろうけど」
「まあまあ、明日に備えて休めたんだから良かったじゃないか」
謙介が笑いながらとりなしたので丈もほっとする。美羽のことは無事におさまったし、わざわざ話して心配させることもあるまい。道江のおしゃべりは続く。
「お父さんたら朝から晩まで締めの言葉を繰り返してるのよ」
「朝から晩までってのは大げさだろう」
「そう? ずーっとぶつぶつ言ってるじゃないの。気をつけないと怪しい人に思われから」
「そうかな。そりゃまずいな」
真顔で眉を寄せる父の様子は珍しいもので思わず丈も笑みになる。
「よろしく頼むよ」
「任せておけ、と言いたいところだが、やっぱり勝手が違うな。何かと迷うよ」
「考えすぎなのよねえお父さんは」
お茶を入れる母に言い切られ肩をすくめる父はこどもみたいだけれど、父と母と自分で三人家族。とっくに一人立ちしていたつもりだったが、今日の今日まで守られていたと思う。感謝の言葉なんて照れくさくて言えそうにない。でも。
「ふたりとも。元気で長生きしてくれよ」
そんな言葉が口をついた。結婚は花嫁だけでなく花婿もセンチメンタルにさせるらしい。父も母も湯呑みを持つ手が止まる。感激屋の道江はあっと言う間にその眼を潤ませていく。驚いたことに父まで、けふけふと咳払いを始めた。まずい。
「いや、ふたりとも丈夫だから心配ないよな。ごちそうさま、父さん仕事に遅れるよ」
あわてて席をたった丈の、背中からはそれでもぐすぐすと鼻を鳴らす音と咳払いがなかなか途切れなかった。
白兎家では家事を片づけながら母娘がおしゃべりに興じていた。
「丈さんて寝起きはどうなの」
「そんなに悪くないんじゃ……お母さんたら何気なくきわどいこと聞かないでよ」
「あら、これってきわどい?」
真顔で母に聞き返されて美羽も口ごもる。
「……少なくともまだ答えづらい」
「そう? お父さんは昔っから眼をあけたとたんに元気なのよね。全身元気ハツラツーってあれよ。ん? これって際どい?」
「聞かなくていいって」
父の茶碗を拭きながら苦笑する。どこかずれているのが母だ。昔から天然と言われたところは明石が死んだあとも変わらなかった。強いと今は思う。
「晩ご飯、なにがいい?」
「お母さんが作ってくれるならなんでも」
「あらら、美羽がそんな殊勝なこと言うなんて。道理で雨ね」
「おかあさん?」
にらんでも母は笑うだけだ。
「暑いから冷やし茶碗蒸しにしましょうか」
「うん。あれ好き」
「卵もしいたけもうどんもあるし。三つ葉がないわ、ああぎんなんも。入れないとお父さんに文句言われそう。買い物行きましょ」
近所のスーパーでののとあれこれ吟味しながら、頭の片隅で美羽は思った。すでに親元を離れて暮らしていたけれど、帰る場所はここだった。明日から丈のいるところが帰る場所になるのか、いやと首を振る。
違うかもしれない。昨日、美羽が待っていたのは丈だった。どれだけ悩んでも父母に打ち明けようとは思わなかった。彼に出会って帰る場所は変わった。明日はそれを誓って認めてもらう日なのかもしれない。
「もう大丈夫ね」
ぱちぱちと瞬きになった。さっぱり梅味のサラダも作りましょうかなんて言ってたはずの母が、美羽に笑いかけている。
「あなたは変に回転が早い分、ひとりでぐるぐると渦を描いて行き止まっちゃうところがあるでしょ」
忘れていた。天然だけど鋭いのが母だ。
「以心伝心なんて言うけど、長年連れ添っても相手の考えはそうそう読めるものじゃないわ。言葉にしないと伝わらないのよ。美羽、伝える努力を惜しまないで。これからは丈さんとふたりで考えてね。どんなことも」
「……お母さん」
「丈さんで良かったって私も、お父さんも安心してるんだから」
勘弁してほしいと思った。右手に大根、左手に水菜を持った母に、タイムセールの店内放送が流れるスーパーで泣かされるなんて。買い物客が怪訝な顔で通り過ぎていく。
「あら美羽、やだこんなところで」
それはこっちの台詞よ、大根で背中たたくのはやめてよ、水菜が折れちゃうでしょ。言いたいことは言葉にならず、人前で泣くのをなんとかこらえるのが精一杯の美羽だった。
らしくもなくセンチメンタルになった丈だが、そこに浸ってもいられない。式の前日、それなりにすることはある。出張で美羽に任せきりだったので、式場の担当スタッフへの最終確認、仲人や主賓をお願いした上司へ電話で挨拶も欠かせなかった。昼過ぎに捕まえた光にはつい文句も出る。
「おまえね、美羽の様子がおかしかったら知らせてくれよ」
葵には美羽を見つけた直後にメールでその旨知らせ、礼を述べてあったので、光にも話しは伝わっていたようだ。
『出張先でキリキリしとる亀さんに? あかんあかん、俺かて命は惜しい』
「あのなあ」
『ウサコちゃんもいまいちはっきりわからへんかったし。どのみち亀さんは仕事が終わらんかったら動けんし。あの時点じゃなんも言えんて』
確かに光の言うとおりだ。終わりよければすべて良しかとため息をつく。
「そそれはそうと二次会の件だが」
『オールオッケーや準備万端。明日は盛り上がるで』
「なんかノリがおかしくないか」
『かまへんて気にせんとき』
「……なんだか不安になる」
『俺と葵が仕切っとんで? 心配いらん』
なるほど。光はともかく葵の仕切りと思えば安心できる。
『式はカメラ持って撮りまくったるからな。社内販売狙っとるし』
「アホバカまぬけ。美羽の写真を売ったりしたら命はないぞ」
『亀さんとカップルやったらどない?』
「はあ?」
『ウサギ神社のご神体になるでえ』
「あのなあ」
がっくりしながらも笑えてしまう。昨日までの疲れや緊張が抜けていく。
「……よろしく頼む」
『へえへえあんじょうやりまっせ。イケメンの花婿さんになってや』
最後まで軽口の光だったが込められた祝いの気持ちは本物だ。友達はいいものだと丈はしみじみ思った。
母と二人で作った冷やし茶碗蒸しは白兎家では馴染みの一品だ。要するに茶碗蒸しを冷やしたものだが、ふつうの具に加えて湯通ししたうどんが入り、大降りの茶碗にたっぷりと一人分。三段重ねの蒸し器が活躍する。蒸し暑い夏にはつるっとした食感が美味しい。久しぶりだったらしく、温が眼を細めて喜んだ。
「いいね。食べたいと思ってたんだ」
「ほとんど美羽が作ったのよ。ねえ?」
「ちゃんと習うのは初めてだったから。簀がたったらどうしようって思っちゃった」
「それも愛嬌よ」
「ちゃんとできてるじゃないか。うん、うまい」
早速食べた温が太鼓判を押す。ののも美羽も口に運んでうなずいた。
「よくできたわ、丈さんにも食べさせてあげてね」
「丈くんにか? もったいないなあ」
「やだお父さんたら」
半分本気に見える温の言葉にふたりが笑った。
一方亀沢家では晩酌が始まっていた。もともとそれほど飲まない謙介は缶ビール一本で足りる。丈も明日に備えて同様だ。道江は謙介のをコップに三分の一ほどもらって三人で乾杯した。音頭はもちろん道江だ。
「美羽さんとの未来にかんぱーい」
「ありがとう母さん」
「いよいよだな」
「わくわくしちゃうわ。自分の時より興奮しそう」
はしゃぐ道江に謙介と丈が良く似た笑みを交わす。
「そういえば母さんと父さんは式挙げたっけ?」
唐突に丈が尋ねると、ふたりはあっさり首を振った。
「再婚同士だったし、入籍だけよ」
「にぎやかなことはしたくなかったんだな、あの頃は」
「今となっては写真くらい撮ればよかったわねえ」
懐かしそうに笑いあうふたり。こんな風に自分と彼女もいつか昔を笑いあえたら素敵だろうな。
「丈さん、美羽さんを大事にね」
「もちろん」
「粗末にしたら私がもらっちゃうから」
「そりゃいい」
「良くないよ」
やっと明日だ。
明日から美羽が誰よりも近い家族になる。
喜びと期待が丈の胸をいっぱいに満たしていた。
白兎家では食後、美羽がアルバムを持ち出した。温が懐かしそうに繰り、ののがのぞき込む。
「赤ん坊の時はほんとに大変だった」
「初めてがふたりだったからよね」
「一緒に泣くんだから」
「一緒におなかがすいてね」
明石と美羽、いつも並んで撮った写真。息子を、弟を、ようやく笑ってふりかえることができるようになった。良いことなのかどうかわからないけれど、楽になったのは確かだ。思い出して語り合う時、明石がいる気がする。丈の言葉がこだまする。
『そばにいる。明石くんみたいに』
明石はきっといる。時にそばで、時に橋の向こう側から、自分を見守ってくれている。だから、大丈夫。
「覚えてるかい、あの日」
「もちろんよ」
「やだ、忘れて」
「丈さんに話してあげなきゃ」
「やめてー」
涙がにじむのは笑いすぎただけ。父も母もそうに違いない。目じりをこすってごまかしながら、美羽は明石に語りかける。
明石?
大好きよ、明石。
明日、見ててね必ず。
夜が更けていく。
結婚式まであと一晩。
next>
|