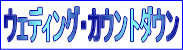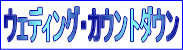|
亀沢謙介はもの静かな男だ。
日頃は声を荒げるどころか、時に何時間も黙っている。
趣味は俳句。休日は散歩しながら気づいた光景、ものごとを書き留める。その後、家でそれらを前にして日がな苦吟して飽きない。その間、声を出すことが珍しい。
しかし、寡黙な男ほど脳内では饒舌だったりするものだ。
仕事から帰って夕飯をすませ、リビングでくつろぐ謙介はいつものごとく寡黙だが、実は頭の中でひとりしゃべりまくっていた。
小さい頃の思い出をひとつふたつ入れた方がいいだろうか。道江との馴れ初めはともかく、丈が彼女に最初から懐いたことは話したい。やんちゃだが優しいところや女性にはもててたこととか。
いやまて、結婚式で親がそれを暴露してはまずいか。あちらのご両親が面白くないだろうし、なんといっても美羽さんがいる。
そうだ、美羽さんとの出会いが丈にとってどれだけ素晴らしいことだったか、それが一番じゃないか。丈だけじゃなく道江にとっても、自分にとっても。彼女と彼女のご両親のおかげで初めて、心の奥底からの安寧を味わえるようになったのだから。
先日、丈は美羽とふたりで謙介の前妻の墓へ参ってきた。美羽が黄色いチューリップを供えてくれたと聞いて思わず顔をほころばせ、謙介は思ったものだ。人と人が出会うこと、縁とはなんと不思議で有難いことかと。
そうだ。
それだ。
思わず拳を握りしめた謙介だが、我に返ってまた思案する。つい思い入れてしまったが、式の最後のお礼をあまり長々としゃべるのは考えものかもしれない。なんといっても締めだ。冗長になっては間が抜ける。
同僚として部下として上司として、あるいは友人として、数え切れないほど結婚式に出席した経験から言えば、スピーチは短いほど歓迎される。長いスピーチは得てしてつまらないものだ。
誰もが知っているのにどうしてああも長々としゃべるのか、時に不思議に思っていた謙介だが、こうして自分の番が回ってきてやっとわかった。話したいことが多すぎる。息子の結婚となればどうしたって思い出があふれて流れて、あれもこれも全部しゃべりたくなるのか。
やってみないとわからないものだな。腕組みしながらひとりうなずいていたら、お茶を運んできた道江にいぶかしがられた。
「どうしたのあなたったら」
「うん? いや」
「披露宴のお礼の言葉、書けたの?」
手元をのぞきこむようにしてくるので、意味もなく手元を隠してしまう。
「まだ考え中だ。結構難しいものだな」
「そう? 慣れてるかと思ったわ」
「どうして」
「主賓でよく出席してたから」
夫婦とはどうしてこう思考回路が似てくるのだろう。
「私もそう思っていたんだが、息子の式でしゃべるとなると大違いだな」
「そうよねえ。お友達からも旦那様が一生懸命下書きして覚えたのに、当日は全く役に立たなかったって話をよく聞くわ」
「それじゃ無駄な努力なわけかい」
苦笑して聞くと妻はにっこり笑う。
「あら、無駄な努力なんてないわよ。丈さんの結婚式の挨拶に頭を悩ますなんて、こんなすてきな経験ないでしょう? それとも代わってあげましょうか?」
おっと危ない。
「いやいやいや、これは私の役目だ」
「やっぱりそう言うわよね」
おやと思った。いつもなら私にも考えさせてとか、あなたばかり活躍する場があってずるいわとかしばらく文句が続くのだが、今日はえらくあっさりしている。
「飽きるまで悩んだら。残り一週間しかないんですからね」
「おいおい、脅さないでくれよ」
「事実を言ってるだけです。書くだけじゃなくて読まなきゃならないんだから。練習するなら聞いてあげるわよ」
「もちろんだ。今日中には書き上げるよ」
「頑張ってくださいな」
それだけで道江はあっさり身を翻した。その軽やかさに少し首を傾げつつも、確かに少なくなった残り時間を再確認させられる。
彼女の言うとおりだ。つっかえつっかえ読むんじゃしょうがない、どちらかというと読み方の方が重要なくらいだ。しかも自分がもっとも苦手な分野ときている。まずい。
道江の入れてくれたお茶でのどを潤し、気合いを入れ直した謙介は、いくつか書きちらした文章に眼を走らせ改めて草稿を練り始めた。
インスタントコーヒーはスプーン一杯。そのつもりだったのに目分量で入れたせいか濃くなった。濃すぎる。冷蔵庫から取り出した牛乳を美羽はほんの少し注いだ。カップの中味がモノトーンマーブル模様に変わる。
ムンクの「叫び」を思い出した。不安を描いたらこうなるのかもしれない。次第に深くなる渦の底にいつか、ひきずりこまれてしまったらどうしよう。
「美羽?」
顔をあげたら母が首をかしげていた。
「カップもって突っ立ってどうしたの」
「え、ううん」
「コーヒー、さめるわよ」
「お父さんは?」
「また部屋でスキップしてる」
視線で笑いあう母と娘。父に万歩計をつけたらこの三ヶ月はこれまでの倍は歩いているにちがいない。
久々の実家暮らしだが、年明けから何かと戻ってきていたのでそんな気がしなかった。どちらかというと昔にもどったようだ。父がいて母がいて。それから、明石が。
ドクン。
動悸にぎくりとした。どうして今。突然広がる雨雲のような不安は馴染みがありすぎる。不安。なにが? 明石はもういないのに。
「美羽?」
母が今度はのぞきこんでくる。
「あなた具合でも悪いの? 顔色が」
「う、ううん。眠いだけ。部屋に戻る」
「眠いならコーヒーはやめといたほうがいいわよ」
「そう、そうね。ごめんおいてく」
口も付けてないカップの中味はすでに一色に沈んでいた。濁ったカフェオレを流しに捨てる。この不安もコーヒーみたいに捨ててしまえたらいいのに。
空のカップを手にぼんやり流しに見入る娘の様子に、ののがやっぱり首をかしげていた。
結婚式まであと7日。
next>
|