|
乙女が生まれ育った家は洋館だ。
高い天井と床。あちこちにガタは来ていたが、上って降りて駆け回るにはぴったりの広さだけはある家だった。5月のちょうど今頃、庭は緑にあふれる。降り注ぐ陽光と家族の笑顔。
思い出すそこにはぼんやりとだが父の顔もある。亡くなった時、乙女は5つだった。忘れ去っても不思議はなかったが覚えている、そのことが今になってとてもうれしい。年を重ねるにつれて父に似てくる兄のおかげかもしれない。
考えが逸れた。言いたかったのは畳にも正座にも縁がないまま成長したということだ。たまに正座を要求される場面になるとそりゃあ苦労した。もうしなくてすむと思っていたのに。
鉄の実家は昭和を舞台にしたドラマさながらの木造二階屋だった。あたりまえだが洋館とは全く違う。直線が生み出す厳しさと美しさ。狭さ故の機能美と木肌の温かさ。先日、初めて訪れた時は気づかなかった細かなところまで今日は否応なく眼に入る。
脳が逃避しているのだきっと。畳の上での慣れない正座。鉄の祖母キヌと向かい合って習ったこともないお茶を頂く羽目に陥れば無理もないと自分を慰める。
鉄ちゃんのバカ。おばあさんて言うのはもっとよぼよぼだったり腰が曲がったり弱々しいイメージでしょ。ぴんとした背筋で粋に着物を着こなし、所作も見事にお茶を点てる人を誰が想像するっていうのよ?
「ばあちゃんが来るんだけど。会うか?」
鉄の言い方は微妙だった。会わせたいようなためらうような。そう突っこんだら頭をかいた。これまで彼女を紹介したことがない上、小さい頃から躾に厳しく母親代わりの部分もあって頭が上がらないという。
「でもさ、乙女は会わせておきたいし」
そう言われたら嬉しくなるのが女心。その気になるに決まってる。結果がこれだ。隣の鉄は乙女の顔色を伺いながらも、正座が全く苦にならない様子がまた頭に来る。
「ちゃんと前をお向きよ鉄。落ち着きのない」
「ばあちゃん、いきなりお点前はないだろいくらなんでも」
一応、鉄なりに抵抗を試みているのは認めよう。無駄みたいだが。
「別に間違っても怒りゃしないよ。笹麩菓子が出たから、どうせなら一緒に食べてもらおうと思ったんじゃないか」
「ふつうのお茶でいいじゃん」
「バカだねこの子は。お茶と食べるのが一番おいしいんだよ」
その理屈はどこかで聞いた気がする。母の小町がいつだか高らかに主張したような。
『これはね、ティータイムのためのお菓子なのよ。紅茶が一番あうんだから。ないならともかくあるなら面倒くさがらないの』
キヌの顔は乙女を惹きつけた。若い頃はきっと美人だったろう。今だって美人だ。美しく年をとる。口で言うほどたやすくはないことの見本とでも言うべきか。それはともかく。
「お点前、お願いします」
かなりぶっきらぼうに言い切ったのはせっぱ詰まっているからだ。とにかく足がしびれきってしまう前に、なんとかお茶を飲み干して立ち上がりたい。しかし乙女の窮状に、鉄もキヌも全く気づく気配はない。
「それにしても見るからに今風のお嬢さんだね。その割に無口で。鉄、どこでみつけて来たんだい」
「ばあちゃん勘弁しろよ。乙女がびびってるだろ」
びびるもんですか。びびっちゃいません。
でもね。
「おやいつもおとなしいわけじゃないんだ。鉄の好みにしちゃおかしいと思った」
「どういう意味だよ。騒々しいのが好みみたいな」
「へえ? 無口なのが好みかい」
「……違うけど」
「そらごらん」
「あっ、あの」
まずいと焦った。うちの家族も話し好きだが、鉄の家族もよくしゃべる。今のところ例外は葵くらいか。鋼といい銀といい、キヌまで。放っておいたらいつまでもしゃべり続けそうだ。なんとか立ち上がる機会を求め、後ろに置いてあった土産を乙女は取り出した。
「これ、母の店で扱ってるスイーツなんです。召し上がってください」
「おやまあ、気を使ってもらって申し訳ないね」
押し出した包みにきちんと頭を下げたあと、意外にアメリカンなのかその場で包みを開けたキヌは嬉しそうに声をあげた。
「こりゃ綺麗だ。おいしそうだね」
乙女が選んだのは抹茶とチョコが二層に綺麗なロールケーキだった。しっとりふわふわの食感が年輩のお客さんにも人気だ。気に入ってもらえそうでほっとした。父親には言いたい放題だったのにと自分でも思うが、怖いものなしの鉄が「怖いんだぞ」と主張した相手だ。
その「怖い」は敬って大事にしているという意味だと思う。鉄の大事な人には嫌われたくない。そういう感情も乙女には初めてのこと。服装がワンピースにカーディガンと乙女にしては無難な線になったのもそういうわけだ。こないだ、家まで送ってくれた鉄が、小町に会ってカチコチだったのをさんざん笑ったけれど、その気持ちが今になればわかるというものだ。
「お茶には合わないかも知れないが、せっかくだから頂こうか」
「俺が」
「あたしが切ってきます。鉄ちゃ、鉄くん台所借りていい?」
「ああ」
「じゃあすぐ……っ」
しまったと思った時は後の祭り。すでに強ばり麻痺していた足先は乙女の意志を全く無視した。
「きゃあっ」
「乙女、大丈夫か」
大丈夫じゃなかった。
正座からひざを突いて立ち上がろうとしたものの、立ち上がれずについた両手に額まで押しつけて平謝りするみたいな形で固まってしまった。血が上ったのか頬が熱い。顔が上げられないのは足のしびれがピークのせいもある。
どうしようどうしたらいいの、ああもう恥ずかしいったら。何年ぶりかの正座なんだからもっと気をつければよかった。鉄ちゃんなんとかして。しんと静まり返った居間でみっともなく突っ伏したまま何秒か、動けない乙女の耳に聞こえたのは。
「ぶーっっ」
……ぶー? ぶーって?
「くっくっくっ、あーっはははっ」
笑ってる。大笑いだ。両肘をついてなんとか身を起こした乙女の前で、キヌは腰を折り腹までかかえて笑っていた。鉄はというとあきれ顔で祖母に非難の眼。
「ばあちゃん」
「ごっ、ごめんよだ、だってさ。足が痺れてるのはわかってたけど、お笑いじゃあるまいにこっ、こんなのはっ、じめてでさ」
「しょうがないだろ、乙女んちには畳の部屋なんかないんだって」
「そっ、そうだろうけどそれにしたってさ」
痺れてるのはわかってた、ですって?
もう我慢できない。
怒りが乙女の全身を駆け巡った。同時に滞っていた血流も勢いよく足先まで押し出されたにちがいない。たった今まで痺れて麻痺していた足指を踏みつけるようにして乙女は断固立ち上がった。ぎょっとする鉄。キヌは大笑いの後遺症で目尻に涙まで浮かべている。
「人の努力を笑ってバカにするのが江戸っ子なんですか!」
「お、乙女」
「鉄ちゃんが大好きなおばあちゃんだって言うから一生懸命我慢してたのに、これじゃただの意地悪ばあさんじゃないのっ」
「乙女、落ち着け」
「お父さんといいおばあさんといい、鉄ちゃんちはなんなのよっ」
「なんだい、鋼がなんかやらかしたのかい」
わめき散らす乙女に動じることなく鉄に聞き返しているキヌがさらにしゃくに障る。
「あたしは鉄ちゃんの好みじゃないそうですっ。あなたもそう言うんでしょっ」
「好みだろうねぇ間違いなく」
「ほらそう言うと……は?」
両手を拳にして怒鳴っていた乙女の頭に、やっとキヌの言うことが届いて驚く。今、なんて? 疑いながらも、寸分動かぬぴしっとした正座で見上げてくるキヌの凛としたまなざしをやっぱりいいと思う。
「あの」
「鉄はお姉ちゃん子でね。姉を自分の好みと混同してたところがあって」
「ばあちゃん?」
「まあそれでもいいかと見てたけど、ほんとのところはあんたみたいに、ぱんぱんと言い返す威勢のいいのが好みだとあたしはにらんでたんだ。それごらん」
「そういうのはもっと早く言ってくれよ」
「言ったって聞くもんかい」
「そりゃまあそうかもしんないけどさ」
「ねえ、あたしを無視しないでっ」
どうしてこんなに怒鳴って地団太まで踏んでるんだか、情けなくなる。おまけに怒鳴りつけたふたりは顔を見合わせ、また笑い出す始末だ。
「鉄ちゃん!」
「あぁもう、とにかくお座り」
座れと言われてぴきっと後ずさる乙女に、キヌが手を振ってみせる。
「違う違う、正座じゃなくていいからさ」
怒鳴って騒いてひどく疲れた。どうでもいい気分でぺたりと内股すわりをした乙女の前に、するりと出された茶碗。
「へ」
まさかこの格好でお点前されるとは思わなかった。
「苦いのがいやだったらそこのお菓子を含んでからおあがり」
取り繕う気も失せた乙女は言われたとおり、笹麩饅頭を黒文字でほおばってから茶碗をおそるおそる取り上げた。わめきちらしてのどが渇いていたから多少苦くても平気だろうとも思ったのだが。
「……おいしい」
これまで飲んだことはあっても正直美味しいと思ったのは初めてだ。濃い緑の泡をまじまじと見る。鉄の安堵した吐息が聞こえた。キヌが彼の前にもお茶を出してやりながら言う。
「結構いけるだろ」
「は、い」
「でなきゃいくらあたしが相手でも、鉄や銀がつきあうもんかね」
「ちっちゃい頃はほんとにお菓子が目当てだったけどな。いつのまにか茶のうまさもわかるようになった」
そう言いながら荒っぽいとはいえちゃんと形をとって茶を飲み干す鉄に、乙女は目を見張った。しゃんと背筋をのばした所作はいつもと全然違ってみえる。うん。
「……かっこいいね」
「へ?」
鉄がびっくり仰天の顔でこっちを向く。
「乙女?」
「男の人がそういうのちゃんとできるって、かっこいいんだ」
「な、んだよバカ」
あわててそっぽを向いた鉄の、首筋から顔まで見る見る赤く染まっていく。乙女の方が恥ずかしくなった。あたしったら何言ってんの。ああ頬が熱い。並んだゆでだこの一対にまたキヌが吹き出す。何度めやら。
「間っ違いないね、ああおかしい。あんたにしちゃ上出来だよ鉄」
「ばあちゃんて」
真っ赤な顔の鉄の抗議は抗議にならない。
「逃がさないように頑張りな」
「ばあちゃんっ」
果たして気に入られたのかどうか、今ひとつ定かでないが確かめる勇気もなく。まだ笑っているキヌを前に鉄と顔を見合わせ、乙女はひどく疲れた気分で肩をすくめた。
その後、鉄抜きで遊びに出かけるほどキヌと仲良くなろうとは、今はまだ予想もできない乙女だった。
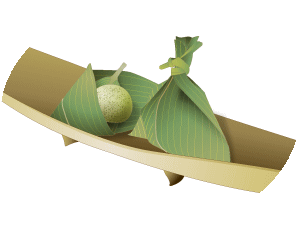
< Gran'ma VS lover / end >
|