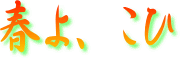 弐、 水に降る雪 |
|
侍は必死に追いかけたが、若者は足が速かった。 一度も振り返らない。前へ前へ、命でも賭けているようだ。 けれど逃がすわけにはいかなかった。 赤子はどこから現れたのか。 どうして自分のところに連れてきたのか。 誰に頼まれて? 誰が? 答えを知るためには、大路にあふれる人波を巧みにすり抜けていく、あの背中をつかまえるしかない。 侍の息が上がってきた。 なんてすばしっこいんだ、全く。年を感じさせてくれるな。 棒手振ぼてふ りにぶつかったのが運の尽きだった。 「気ぃつけな」 「すまん」 目をそらした間に、確かにあった背中が消えて、侍の足が止まる。 しまった。 大路を西から東へ半分来たところだった。つまりは京の真ん中だ。ここから東西南北、どこへでも行ける。どこへ行ったのか見当もつかない。 「参ったな」 とりあえず東へ向かった。あの、引き絞られた弓から放たれた矢のような勢いが、すぐに止まるとは思えなかったから。的はどこにあるのか。 しばらく走ると、どこかで悲鳴が上がった。 伝わってくる響きは、懇願と絶望だ。 走る方向を少し南へ変えると、また声がした。しかもたくさん。 今度は間違いなく聞き取れた。 「身投げだ!」 「子どもか」 「女だ」 「舟がいくぞ」 たどりついた河原には人垣ができていた。注がれているのは好奇の目、憐れみと安堵の目。他人の不幸で自分の今を計る辛辣な目、目。 その隙間から、舟で引き上げられたらしい土左衛門が土手に寝かされているのが見えた。とりすがっている背中はさっき見失ったばかりの。 「通してくれ、頼む」 人垣を抜けて出たそこで、侍は二度目の衝撃を覚えた。冷たくなって動かぬ体、その顔が記憶をかすったから。ひらひらと舞う赤い尾びれと、悲しげな笑顔が。 「……金魚?」 ずぶぬれの肌は透き通るように白く、閉じた目はもう開くことはないのに、紫色の口元はなぜか笑んでいた。ぐったりと広がる髪も雪が白く化粧していく。 「姉ちゃん! 姉ちゃん!」 若者の声にさっきの意地や強かさはみじんもない、母親を呼ぶ子どものようだ。その向こう、かけつけた同心と苦々しく話しているのは、どこかの店の男衆おとこし らしい。 「急に姿が見えんようなって、ややこ連れなんで遠くには行けん思うとったら、身投げやなんて」 ややこ。 死んでなお握りしめている赤い布が、侍の目をさらった。 あの子を包んでいたのと同じだ。 「このガキも息子か」 同心の問いに、男衆は不機嫌に手を振った。 「この女がどこかで拾うてきてん。あんまり頼むんで、下働きにおいてやったんや。借金も残っとるのにガキは拾うわ、ややこは産むわ、そんで身投げてかなわんわほんま」 珍しい話ではなかった。遊女も拾い子も、それをこきつかう者もたくさんいる。腹を立てるほど自分は善人ではない。だがこの場で言うのはあまりにも心ない。 「なんで身投げしたんや」 「ややこの種が来んようになったらしい。どこの種やら金輪際言わんかったけどなぁ。お産で弱って変な咳がついて、一年経ってもろくに客もとれんで、前途を悲観したっちゅうとこやろか。あぁうるさいわ」 舌打ちした男衆は若者を死体からひきはがし、突き飛ばした。 「ちょうどええ、おまえもどっか消ええ。店に男は余っとるんや」 「姉ちゃん」 「消ええ言うとろうが」 「俺も死ぬ、死んだほうがええ」 「ほんならそうしたろか」 「あほ、なにするんや」 「やめろ」 男衆は若者の胸ぐらをつかみ締めあげる。同心があわててひきはがした間を、侍が割った。無慈悲な人垣は興味を失ってばらばらと散っていく。 同心の手を振りきって、男衆が侍をにらんだ。 「なんやあんた」 「通りすがりだ。あんまり非道をするもんじゃない。お払い箱というんなら俺がこの子をもらおう」 「なんやて」 「殺すより面倒がない。しょっぴかれもしないぞ」 迷ったのはわずかな間で、男衆はふんときびすを返した。半纏の背中には『雁屋』とあった。 「同心の旦那、女はもろうていくわ」 「わかった」 「やめえ、連れてくな!」 なおもすがろうとする若者を、今度は侍が押さえねばならなかった。それを鼻で笑って男衆が言い捨てた。 「二度と顔見せんなよ、遠矢」 とおや。 誰かが言わなかったか? 『矢を離すな』 考える間に、持ち込まれた戸板で女は運ばれていく。 「姉ちゃん! 姉ちゃん!」 見えなくなるまで叫び続けた若者は、やがて精根尽きたように黙った。侍が手を離してもぼんやり立っている。あれだけ叫んでも涙がないのが、かえって哀れだ。 河原には誰もおらず、何も残っていなかった。いや? 赤い布地が落ちている。血のように赤い。拾うとぐっしょり冷たかった。冷たすぎる。 ばっとそれを奪ったのは若者だった。布を握りしめた拳を額に押しつけ、小さく何かつぶやくと、不意に川へ向かって駆け出した。 すかさず侍が足を引っかけたので、若者は前のめりに水際の砂利へ突っ込んだ。そのまま動かない若者を引き起こし、顔を見据える。 「どうして俺のところにあの子を連れてきた」 「あんたの子やろ」 「違うとおまえは知ってるはずだ」 青ざめた顔。目は絶望を映している。たったひとりの死を。 「それでも姉ちゃんがそう言うたんや。あんたならきっと守ってくれるて」 金魚。 「知ってたのか。姉ちゃんが……死ぬつもりなのを」 若者は答えずにのろのろと川を見た。それから川上の橋を。 「……姉ちゃんが見えた。欄干に立っとった。姉ちゃんも俺を見つけて、笑うた。かんにんてつぶやいて」 そして、身を投げたのか。 「待ってろ言うたのに。もうちょっとやったのに。もうちょっと早う戻ったら一緒にいけた。ひとりで死なさんかったのに」 「おまえには生きて欲しかったんだろ」 侍へと振り返った若者の目には、絶望を押しやるほどの怒りがあった。 「姉ちゃんがおらんのに、生きてなんになるんや! 誰もおらん! ひとりや、またひとりや!」 「ひとりじゃない」 侍は淡々と答えた。 「聞いてなかったのか。おまえは俺たちと暮らすんだ」 ぽかりと若者の口が開いた。 「ほ、んきやないやろ。春吉もおるんやで。なんでその上」 「おまえも大事な届け物だ」 「……なんやて」 「姉ちゃんは、おまえも一緒に届けたんだ。俺のところへ」 守ってくれと。 「おまえのことも、大事だったから」 若者の目が揺れた。張り付いていた氷がふるっと溶けて、涙があふれだす。その頭を侍は自分の胸に押しつけた。獣が吠えるような泣き声が響く。その手に握りしめた布が風にひらひらたなびく。 かんにんと聞こえた気がした。 かんにんねぇ、旦那。 バカだな、金魚。 川面に雪が溶ける。 はかなすぎた命を、侍は悼んだ。 次 >> |
|
| <Home <侍目次 一< >三 | photo /clef |
|
シリーズ物なので、この番外から読まれる方は少ないと思って(願って?)いますが、 忘れていらっしゃる方は多いかも。 サイト八周年短編集「春夏秋冬」の七話を、再読頂けるとわかりやすいです。 さよなら、金魚。 お気に召しましたらぽちっとお願いします。 ご意見ご感想もお待ちしております。 ↓ |
|