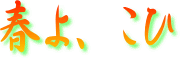 一. 藪入りの客 |
|
土手で足を止めた娘は、浅縹あさはなだ 色の空を見上げた。 凧たこ が三つ、北風に身を晒している。ぐいぐいと胸を張って競う様は、地上で糸を操る子ども達にそっくりだ。足を踏ん張り頬を真っ赤にして、懸命に自分の凧に声をかけている。 「あがれ、あがれーっ」 『寿ことぶき 』 と 『纏まとい 』 の字凧が少し上になる。宝船の鮮やかな絵凧は値が張りそうだが、糸をたぐる身体に比べて大きすぎるようだ。 思う間に絵凧はくるくる回って落ちた。操っていた子も転んでいる。娘はあわてて土手を駆け下りた。 「大丈夫?」 糸を握りしめている男の子は六つか七つくらいか。泣きべそをかいていたが、娘に声をかけられて恥ずかしくなったらしい。 ぐいと目元を拭って立ち上がると、ものも言わずにまた駆けだした。引っ張られた凧は地を這ううちに風をはらみ、再び空へと舞いあがっていく。 あがれ。 あがれ。 天まで上がれ。 藪入りの今日、里帰りした家から凧を抱えて飛び出す子は、他にもいるに違いない。落ちても落ちてもあきらめない子どもは眩しい。 娘は土手を離れ、歩きだした。 今年の雪はまだ浅かった。年末年始の冷え込みが緩んだせいもあって、道のところどころに土が見える。 寺の境内も白と黒が入り乱れて模様のようだった。白黒の土を踏み、掻き残した雪が隅で凍っている石段を慎重に上ると、墓所があった。 「鏡開きのお裾分けよ。みかんもね」 小さな墓の前に、懐ふところ から取りだした餅とみかんを供え、手を合わせた。向こうに広がる山まで静けさが張っている。 突然、ふわりと心に降りてきた思いを、娘は静かに受け入れた。 もう、身ごもることはないのかもしれない。 目を開けると心なしか空が明るい。狂ったように蝉が鳴いていたあの日からずっと、絡みもつれていた心の糸が、やっとほどけた気がした。うつむくと、斜めに伸びた淡い光が、娘の膝頭まで手を伸ばしている。 寂しい? そうね、あたしも寂しいけれど。 必ずいくから、向こうで待ってて。 娘が立ち上がると、まとわりつく子犬のように光が足元にわだかまる。墓標を指で撫でてから、娘は寺を後にした。 ゆっくりと戻ってきた娘は、赤子の声を聞いた気がして足を止めた。あたりを見回しても誰もいない。いぶかしく思いながら道場の門をくぐると、若者がひとり、庭に立っていた。 十五、六だろうか。細いけれどしっかりした体つきは、大人と子どもの境目だ。髪は無造作に紐でくくっている。つんつるてんの着物から伸びた長い手足が目立つ。素足にぼろぼろの草履が寒々しい。 腕に何か抱えていた。真っ赤な紅絹もみ 地の包み。泣き声がまた、そこから。思わず駆け寄ろうとしたら、若者は咄嗟に背中を向け、娘をにらんだ。 「あんた、誰や」 逆毛だった猫のような目。威嚇に、怯えが隠されている。 怖がらせたくなくて、娘は立ち止まった。 「この家の者よ。あなた誰? 泣いてるのは赤ん坊?」 「こっちぃ来んでええ」 激しく拒み、首を振る。その間も泣き声は止まない。 なんとか落ち着かせようと両手をあげた。 「何もしないわ。あなたこそ用があるんじゃないの?」 めくらうちだったが、当たったようだ。若者は包みを抱え直して、誰かを捜すようにあたりを見回す。 「ここに、お侍がおるて聞いたんや」 「お侍?」 「おるなら呼んでくれ。会わんとならん」 「わかったから」 泣き声を気にしながら、仕方なく娘は道場へ走った。 縁側から侍を呼ぶ。 「あなたに用があるって」 「誰が」 稽古の途中だ。侍は厳しさを滲ませて縁側に出てきたが、娘の視線を追って面食らった顔になる。草履をつっかけて庭に降りた。 「俺に何の用だ」 値踏みでもするように侍を見ていた若者の表情が、一段ときつくなった。ずかずかと侍の前まで行くと、包みを突き出し、押しつける。 「頼まれたんや。あんたに届けて欲しいて」 受け取ろうとした包みが解けた。のぞいたのはやっぱり赤子だ。生まれて一年過ぎたくらいだろうか。侍が驚きで目を見張る。 「俺に? どうして」 「名前は春吉はるきち や」 「だからどうして」 若者は腹立たしげに言い放った。 「あんたの息子やろ」 「……なんだって?」 「むすこ?」 素っ頓狂な声をあげて、侍と娘はその場に固まった。赤子がまた泣き始める。母屋から内儀が、老師も飛び出してくる。 「どうしたの」 「なんじゃ、どうした」 多勢に無勢と思ったのか、それとも潮時と思ったのか、侍を指さして若者は叫んだ。 「ええな、渡したからな。粗末に扱うたら承知せんぞ」 言い捨てるや身を翻して門から飛び出していく。ぼうっと見ていた娘の腕に赤子が押しつけられた。 「頼む」 我に返った時には、侍もその場から消えていた。夢でも見ていたようだが、腕の重みは夢ではない。泣き声も。 「……どういうこと? その子は?」 「息子とか言わんかったか?」 娘を囲んだ内儀も老師も、娘と同じく夢から覚めきらないような口調だ。 赤子だけが現うつつ だと訴え、泣き続けている。 藪入りの客の声に応えるように、はらりひらりと雪が舞い落ちてきた。 次 >> |
|
| <Home <侍目次 >二 | photo /clef |