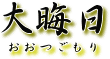 |
|
ゆらゆらと灯りが揺れた。 疲れた眼がちらつくのをこらえ、娘は針を引き抜く。丁寧に玉留めしたあとを始末すると、糸を残した針を針山に刺した。ほっとしながら凝った肩を手で揉む。 膝の上にあるのは娘の晴れ着だ。侍といちのはとうに縫い上げてあった。自分のを後回しにするのはいつものことだが、悪いくせだと夕べも侍に叱られた。 「いちはともかく俺より自分のが先だろう。遠慮することじゃないぞ」 「遠慮してるわけじゃないもの」 囲炉裏いろり ばたの斜め前に座した侍は、針を持つ娘の方へと行かぬようにいちを遊ばせながらぶつぶつ言っている。娘は縫う手元からふたりへと視線を添わせる。 「いちや貴方のは縫う前から、似合うだろう似合うようにって心が急せ く上に楽しいから、つい」 娘の言い訳に仕方のない奴と苦笑しつつ、侍はいちの相手を続けてくれた。暮れの雑事、正月の準備に追われながらなんとか間に合ったのも、そのお陰だ。 縫い目をならしながら確かめた娘は、灯りを消し囲炉裏の火を埋めると立ち上がった。 しんと冷えた縁側に比べると、入った寝間はぬくみがあった。仄ほの かに浮かぶ行灯あんどん 。いちを寝かしつけようとして眠気に誘われたのだろう。添い寝した侍は頬杖ついてうつらうつらしている。 娘が、部屋の隅の衣桁に縫い上げた晴れ着をかける気配で眼をさますと、身を起こして胡座をかいた。数歩あとじさりして眺めている娘に声をかける。 「間に合ったな。いいじゃないか」 ふりむいた娘は嬉しそうに頷くと、蒲団のそばにやってきて膝をつき、いちをのぞきこんだ。くうくうと安らかに上下する小さな身体。投げ出された両手両足。眠る赤子ほど見ていて心安らぐものはない。 「大きくなったな」 侍の声に潜む感慨。見上げた娘の肩が引き寄せられ、少し冷えた肌が大きな温もりに包まれた。心地よさにほーっと息を吐いた娘は、子どものようにその胸に頬をこすりつけた。 「ありがとう。いちをみていてくれて」 「縫う方は手伝えぬからな。さすがに針は馴染みが薄い」 くすくすとくぐもった娘の笑いが互いを暖めた時だ。 冬夜の鎮まった闇。 厳かな音が響いてきて、ふたりは顔を見合わせた。 「ひとつ」 娘がつぶやく。 「ふたつ」 侍が唱える。 みっつ、よっつ、いつつ。 ゆったりと余韻を含んだ鐘の音は次第に増えて、いくつも重なり数えることも難しくなるが、どれもが留まらず急がずに夜を渡ってとどく。 いくつの鐘が鳴っているのだろう。娘は思う。今、京で一体どれだけの人がこの音に耳を澄ませているのだろう。 じわっと突然、娘の目頭が熱く潤んだ。あわてて侍の胸に顔を埋めるが、滲んだ滴はごまかせなかったらしい。侍におとがいをつかまれ顔を上げさせられる。 「どうした」 「違うの。悲しいんじゃないの」 ふるふると首をふって娘はなんとか笑おうとする。 「一緒にいられるのが嬉しくて」 去年も決してひとりではなかった。亭主が、老師が内儀が、たくさんの人が娘を支えてくれた。それでも。 まだ見ぬいちを腹に抱え、音沙汰のない侍を待ちながら聞く鐘には、どうしようもない心許なさと寂しさがあった。翌年、こんなに満たされて聞くことができるなんて、あの時は夢見ることすら難しかった。 「嬉しかったの」 繰り返す娘の唇は侍のそれにふさがれた。ついばむような優しさがゆっくりと深いものに変わろうとする。息を求めてふと離れた隙間にごーんとひとつ、鐘が挟まる。侍が囁く。 「来年も再来年も。すぐにいちも起きて一緒に聞くようになるさ」 頷いた娘の微笑みはやっぱり、涙でにじんでしまう。目元のしずくを吸い取った侍は、娘を横たえるとふたたびその唇を求めた。 互いの熱が移る。娘の全ては侍に溶けていく。 繋がり結びあう身体と、心。 大晦日おおつごもり の夜。 降り積もる雪のごとく誰の踏み痕もない新しき年は、鐘の音の終わりとともにふたりを訪おとな なったのだった。 < ootugomori / end > |
|
| <Home <侍目次 | < 背景 / Kigenより > |
お気に召しましたら、ポチッとおしてやってくださいませv ↓ |
|