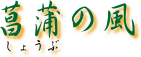 |
|
通りの桜はすっかり青葉だ。 花見が終わるのを待ちかねたように下生えの草も元気に生い茂り、紫陽花が梅雨をにらんでこんもりと葉と背を伸ばしていた。 「やっぱりやめといたほうが」 「大丈夫ですって」 「ほらこない言うとるやろ」 宿屋の昼過ぎ。部屋はどこも静かだというのに、亭主の部屋はかしましい。女将が初めて、赤子を置いて亭主と出かけようとしているのだった。 娘はもちろんのこと使用人たちも安心しろと胸をたたいてくれた。我が家で、信頼できる相手に預けるというのに、女将はぐずぐずと腰をあげられない。 「わかってます。ほかの誰に頼むんより安心なことくらい。それでも子どもはなにがあるかわからへんし」 「おなか一杯でくうくう寝とるやないか。なんぞあったらすぐ知らせるよう言うてある」 「ちょっとでも具合がおかしかったら、お医者の先生のところへすぐ駆け込みますから」 「そやけど」 「ほんまに頼むわ、今日あんたをお披露目せんかったら、商人仲間になに言われるか」 困った顔でしかし浮かべる笑みは、惚れ惚れするほど大人の男の魅力にあふれている。女将と娘を得て、亭主は一段と男ぶりをあげたようだ。 娘がそう思うのだから、恋女房はなおさらだろう。みつめられて頬を赤らめる。その色香は芸妓の頃よりもさらに艶を増し、同じ女である娘ですらうっとりさせられる。似合いの一対だ。 「すんまへん駄々こねて。恥ずかしいわ」 「ええやろ身内しかおらんのやし。見せとうない子は夢ん中やしなあ」 亭主がのばした指先でいとおしげに赤子の頬にふれる。触れて、呼ぶ。 「菜菜、ええ子で寝とってや。おとうはんとおかあはんはすぐ、戻ってくるさかいなぁ」 なな。それが赤子の名だ。 やわらかい響きがふんわりした赤子によく似合う。 初めて名前を聞いた時、いちは飛び上がって喜んだ。てっきり数の七だと思ったらしい。そうじゃないとわかるとおかしいくらいがっかりしていた。 「あたしの妹分だから七だと思ったのに」 「そうか、そら悪かったなぁ」 「どうして違うの」 赤子を抱いて座るいちの頭を亭主の手のひらがぽんぽんと撫でる。 「生まれたんは春やろ。菜の花の黄色がえらいきれいで。女将も好きな花や言うから」 「ふうん」 「呼びやすいしな。いちとなな。絶対間違わんやろ」 「あたしと?」 「そや。いちの方が幾つもお姉さん、年上や。間違うたらあかん。あてる字が違うだけでいちの妹分やし」 「……菜菜っていい名前かも」 亭主が説くといちはあっさり陥落する。 「おおきに。ええ子やなあいちは」 赤子ごとぎゅっと抱きしめられて赤子の抗議と同時にいちの笑い声があがる。娘が覚えた安堵には他の理由もあった。 生まれてこのかた、いちは亭主のいわば秘蔵っ子で、その座を奪う赤子に焼き餅を焼いたりしないかと心配していた。亭主にすればようやく生まれた我が子が一番かわいくてあたりまえだから。 なのにおくびにも出さず、いちをたててくれる。女将もそうだ。その懐の広さ、温かさは親として見習わねばと娘は自戒したものだ。 「ほな行ってくるわ」 「お願い申します」 すがるように娘の手をにぎってくる女将を安心させるようにほほえむ。自分にも覚えがある。初めて我が子と離れる母親の気持ち。 「いい子で待ってますよ」 ほかの使用人たちと一緒にふたりを送り出した娘は、赤子の眠る部屋に戻った。女将の気持ちを思いやって赤子から眼を離さないつもりだ。 部屋にいても仕事はいくつもある。洗ったおむつや肌着はもちろん、客の浴衣や手ぬぐいの片づけつくろい、次から次だ。赤子は穏やかに眠り続けてくれたので仕事も捗はかど った。一段落してほうと手元を休める。 静かだ。 ふと床の間をみやった娘は飾られているのが菖蒲しょうぶ だと気づいた。花菖蒲と呼ばれるアヤメ、カキツバタの華やかさに比べると、地味な花は黄緑色のがまの穂のよう。葉がくっきりとりりしく幅広の刀を思わせる。 ああと思った。端午の節句だ、忘れていた。いや心に留めないようにしていたのかもしれない。ほんとうなら。 んぎゃ、と赤子の声に我に返る。んぎゃんぎゃと人恋しげに求める。いざりよっておむつを代えてやったが、甘えるみたいにむにゃむにゃ泣くのでつい抱き上げてしまう。冬生まれだったいちに比べると、春生まれの菜菜は華奢で優しげに感じる。 三月、初節句の祝いの時、よたよたと歩き始めた菜菜を見て亭主夫婦はそりゃあもう大騒ぎだった。歩いて転んでまた立ちあがる赤子に、娘も一緒になって声をかけ、喜び笑った。久しぶりに声をあげて。いちが眼を丸くしてからとびついてきた。見上げると侍が笑んでいたっけ。 あれからふた月。足もずいぶん達者になり体つきもしっかりしてきたけれど、抱き上げた菜菜はまだまだお乳の匂いがした。つんと、出るはずのない娘の胸乳が痛む。甘い香りと痛みの記憶が交差する。 こうして抱いてやれなかった子。ほんとうなら初節句だった。葉を巻いた刀を持たせていちと遊ばせたかった。侍と菖蒲湯に入れてやりたかった。きっとどちらも喜んだだろうに。 おぎゃあと鋭い声が手元から沸き上がった。ぼんやりしていた娘に訴えるような。まずい、おなかが空いたのか。台所に言ってお粥をもらってと頭で考えるのに、心はまだ彷徨って赤子を離せない。 生まれた時、こんな風に元気に泣いてくれていたら。 「ほら、泣いとおす」 「ほんまや。おみそれしたわ」 足音も聞こえなかったのに。振り向いたら亭主と女将が息を切らして並んでいた。 「置いてってかんにんなぁ。おたぁはんどすえ」 驚きながらも娘はのばされた女将の腕にまだ泣き続けていた赤子をわたす。とたんに泣き声が止んだ。母親だとわかったのだろう。 「へえへえ、おっぱいどすな」 「お粥やないんか」 「ええの。寂しかったんどす」 「あんたが? 菜菜が?」 「どっちも」 「へえへえ」 からかいながらもとろけるように妻子をみつめた亭主は、娘の顔をみて決まり悪げになった。驚きを取り違えたらしい。 「帰りが早かったやろ。行ってからもそわそわしてこっちまで落ち着かんでな。おまけになんとか顔見せして愛想笑いした思うたら、急に帰らなあかんて言い出して」 「泣いとるんがわかったからどす」 「なんでて聞いたら」 「お乳が張ったんでしょう?」 娘の答えに女将は我が意を得たりとうなずき亭主が眼を丸くする。 「そういうもんか」 「子を産んだおなごならわかります。なあ?」 穏やかな呼びかけに素直にうなずけるのは、女将が自分と同じつらさかなしさを知っている人だからか。 乳をやる母子の間にある人知を越えたつながりも、あの子とは感じるいとまがなかった。胸をくつろげる女将と赤子からそらした娘の視線が、また菖蒲に止まる。 かつての底なし沼のような悲しみではないけれど、透き通る影のような寂しさは止めようがなかった。 そこに、また。 「旦那さーん、女将さーん」 腹のそこまでびんびん響く声の主は、もちろんいちだ。風呂敷包みをぶらさげて駆け込んでくる姿。 ちゃんと挨拶しなさいといつも叱られるのに、言いたいこととか気になることがあると行儀よりも気持ちが先んじる。子供だから仕方がないのだろうが。 「いち、ご挨拶は」 「あっ、ごめ、じゃなくて」 「ええて。うちはいちには我が家と同じや」 「ほんまに。かしこまったりしたら怒りますえ」 とりあえず黙ってはいるものの、いちの顔つきがほらほらと得意げになるので娘はまためっとにらんでやる。首をすくめるいち。なだめるように亭主が聞いた。 「なんや、おとうはんはまだかいな」 「走ってきたから。これ、おばあちゃんがどうぞ召し上がってくださいって。すっごく美味しいの」 風呂敷の中身はこぶりの重箱が二段。そのどちらにも柏餅がぎっしり詰まっていた。お乳をやりおえた女将が赤子を抱いてのぞきこむ。 「あれまあこないに仰山」 「こらうまそうや」 言うそばから亭主の手がのびる。 「うん、うまい」 「あたしも手伝ったんだよ。あんをこねるのと皮で包むの」 「ほんま? どれどれ?」 「これやろか」 確かに少しいびつであんがはみだしそうなのを、女将はすっと手にとってためつすがめつ眺めた。 「上手に包めてはる。いちはほんまに大きゅうならはったなぁ」 「女将さん、菜菜は食べられる?」 なるほどそれをねらっていたのかと娘は苦笑した。歯は生えてきたが柏餅はどうだろう。しかしにっこり女将は笑む。 「あんこをちょっぴりあげまひょなぁ」 二つに割ってのぞいたあんを白くて細い指先が少しだけすくう。芸妓の頃はきれいにのばしていた爪もごく短い。それも母親らしい。 おなかいっぱいの赤子はにぎやかさに気を取られて、くうくうと丸い眼をきょろきょろさせていた。その口元にそっと差し出される指先。 「菜菜、ほら」 あっさり吸いついた赤子ははむっと舌で巻きとった味に眼を見張り、それからにまっとした。それをみていちが大喜びする。 「笑った、笑ったよ」 「うまかったんやろ。甘いしなあ」 「いちが作ってくれはったんどす。美味しいに決まってますえ」 「うんっ」 「いちじゃなくあておばあちゃんが、だろうに」 いつのまにか侍が皆のうしろにいた。 「手柄を独り占めはどうなんだ、いち」 「ちゃんと言ったよ。おばあちゃんからって。でもあたし手伝ったもん」 「そうか。で、肝心のことはおかさんに言ったのか」 「あ」 いちの我の強さが一転弱まる。苦笑した侍は娘に手元を掲げた。小さな包みがもうひとつ。いちが叫ぶ。 「柏餅、お墓にも供えてあげようよ。お節句だもん」 再びの胸の痛みはふたりの笑顔に鈍く溶けた。赤子を亭主に渡した女将が庭先から水桶をとってくる。床の間と同じ菖蒲がひと束。 「男の子ぉはこれが要りますやろ」 「菖蒲刀なぁ。なつかしわ」 「お餅と一緒に供えて、な?」 「……ありがとうございます」 皆の優しさが娘の胸に沁み入った。 悲しみは消えずとも、ふりつもる人の温かさに癒されていく。 だから、大丈夫。 いちが包みを侍が水桶を持ち、間を娘が手でつなぐ。ゆっくり茜に滲み始めた空。三人の後ろから三つの影が仲良くついてくる。 薫る五月。 菖蒲の香る風が流れるように夕焼け空へ吸い込まれていった。  < shobu no kaze / end > |
|
| <Home <侍目次 | photo /植物園 |
|
お気に召しましたら、ポチッとおしてやってくださいませv ↓ |
|